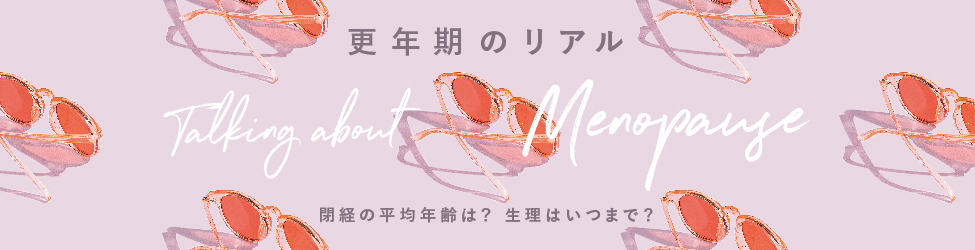その部屋に二人きりで白昼過ごすの?不倫妻の大胆すぎる逢瀬は
後ろ指をさされる関係とわかっていても、やめられない不毛なつながり。
不倫を選ぶ女性たちの背景には何があるのか、またこれからどうするのか、垣間見えた胸の内をご紹介します。
前編はこちら【不倫の精算#20後編】
これまでの記事はこちら
唖然としてしまう。堂々と不倫を続けるための「計画」
Gさんと彼の関係は順調だったが、家が遠くクルマで片道30分ほどかかるのが悩みだった。
「彼は親から相続した家に住んでいるから、もう引っ越しができないの。
わざわざホテルに行かなくても彼の家があるからラクではあるけど、移動の時間がもったいないのよ」
クリームを入れたカップをスプーンで混ぜながら、Gさんは小さな声で言った。
「だからね、私が行こうかと思って。あっちに」
「え、みんなで引っ越すってこと?」
思いがけない言葉に、思わずこちらの声が大きくなる。
この反応を予期してだろうGさんは、慌てて早口で続けた。
「違うよ、私の仕事専用の部屋を○○市で借りるってこと。
そうすれば堂々と家を出られるし、彼とも会いやすくなるでしょ」
彼の住んでいる町ではなく、ちょうど中間にある市に小さな部屋を借り、そこで仕事をする。県の中心部であるその町には仕事の取引先もあって、「仕事の都合」として家族に説明すれば、あやしまれることはない。
彼の家までそこから10分ほどであり、彼が都合のいい時間にGさんに会いに来ることもできる。
これが、Gさんの計画だった。
その生活は破綻しているから…「正論」なんて誰もいらない
「でも、家でもできるのにわざわざ別に部屋を借りるって……旦那さんとかご家族のかたは反対するんじゃない?」
そう尋ねると、
「そうね。
でも、いま私のほうが夫より収入が多いのよ。
夫より稼いでいるのに家事も育児も私ばかりがやっているの。
それはあの人もわかっているのよ、プライドが傷つくから絶対に触れないけどね。
だから、それなら、“もっと集中して仕事をしたい”って言っても反対はできない。
結局大変なのは私だけなんだから、文句もないでしょ」
Gさんは投げやりな口調になって答えた。
だが、いまは在宅で仕事をしているから家事も何とかこなせているに過ぎない。別に部屋を構えるとなると、往復の通勤時間が発生し、明らかに家事がこなせなくなるだろう。
それでも、
「私が稼げているからこそ、もっと集中できる環境がほしいと言えば夫は従わざるを得ない」
それがGさんの予想だった。
それなら、まずは家事や育児の分担について夫と話し合い、そこまでしなくても仕事ができるよう整えるのが夫婦だろう、という思いが浮かんだ。だが、Gさんの望みはあくまでも「不倫相手の彼ともっと会える環境を手に入れる」ことであって、そんな“正論”は今まったく不要であることは、すぐにわかった。
でも、もし夫に踏み込まれたら…?
「彼は何て言ってるの?」
そう尋ねると、Gさんはぱっと笑顔になった。
「もちろん賛成よ。
ネットで物件を探して、安くて良さそうなものがあったら情報を送ってくれるの。
駐車場が2台必要になるからそこだけはどうしてもお金がかかるけど、部屋自体は別に古くてもいいの。ネットの環境だけ用意できれば仕事はできるし」
と答えた。
Gさんは本当に新しく部屋を借りてそこで仕事をし、合間に不倫の彼との逢瀬を楽しむつもりでいる。
「家賃についてはね、一応彼も少し出すって言ってくれて。
彼のせいじゃないんだけど、申し訳ないわよね、気を使わせちゃって」
と、まるで恋人と同棲をはじめるような浮かれ方をしていた。
だが、彼女は気づいているのだろうか。
その市にはGさんの夫が勤務する会社もある。まさか仕事用に借りた部屋の住所を夫に隠すわけにもいかないだろう。把握されたならいつ訪ねてくるかわからない。
そのとき、不倫相手の彼と一緒のところを見られたら、幸せはあっという間に終わるのだ。
「ねえ、あのさ、あなたの旦那さんと鉢合わせする可能性とかは? 大丈夫?」
恐る恐る口にすると、Gさんの瞳にさっと陰りが走ったのが見えた。
そもそも、夫は私に微塵も興味を持っていない
「もちろんよ。
あの人の会社からなるべく遠くにするつもり。
それに、どうせ私が何をしたってあの人は関心がないんだから、来ようなんて気も起こらないわよ」
中を飲み干したカップに目を落としながら、Gさんはつぶやいた。
そう、夫の無関心を誰よりも感じるからこそ、こんな“決断”ができるのだ。
何をしていたって、夫は収入が自分より高いことに嫉妬し続け、モラルハラスメントを繰り返すことで溜飲を下げる。妻の大変さを見ようとはしない。
仕事部屋が実は不倫相手との逢瀬の場でもある事実など想像もしないだろうし、そもそも訪ねるほどの愛情も、興味もない。
それを一番知っているのがGさんであり、この大胆な計画は、夫への意趣返しでもあるのかと感じた。
「ねえ」
伝票を引き寄せながら声をかけると、Gさんはゆっくりと顔を上げてこちらを見た。
「仕事、うまくいくといいね」
力がこもらない言葉に、Gさんは曖昧な表情を作って頷いた。
自分の選択は「破滅の入り口」でもあることを、誰より覚悟しないといけないのは彼女だ。
きっと、それもとっくに気がついているはずなのだ。
<<この話の前編はこちら
■(編集部より)30~60歳の女性の皆様!
「気になる?ひじ、ひざについて」ぜひぜひアンケートにご協力ください。
>>>こちらから
スポンサーリンク
【注目の記事】
- 思春期ど真ん中の高2男子が変わった!ゲームと動画で夜更かし三昧→翌朝起きられない…のダラダラ生活が、スマートウオッチつけたら別人級に
- 40代以降の「肌の変化」どう向き合う? 赤のジェリーでおなじみ「アスタリフト」たった7日試しただけで「わかったこと」とは!
- 【強烈寒波の防寒はコレ!】48歳「冷えに悩む」PTA中受ママが「温活にハマった」結果、家でも外でも「つけっぱなし」!暖房代も節約できるあったかグッズとは?
- 【強烈寒波の防寒はコレ!】48歳「冷えに悩む」PTA中受ママが「温活にハマった」結果、家でも外でも「つけっぱなし」!暖房代も節約できるあったかグッズとは?
- 脱・着太りにやっぱり頼れる【ユニクロ】。真冬の屋外イベントも怖くない、防寒と美シルエットを両立したダウンコーデ【40代の毎日コーデ】
スポンサーリンク