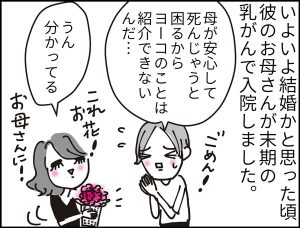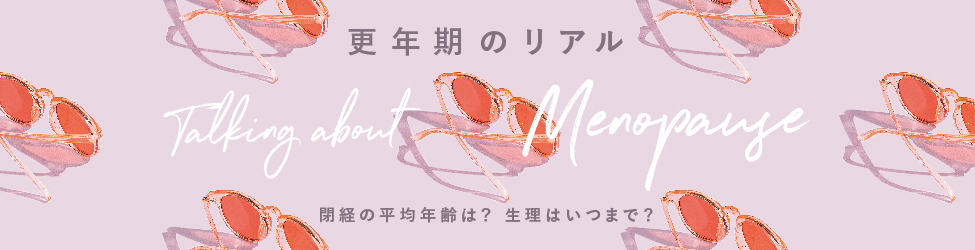50歳なのに「頑張ってくれる」カレ。この不倫、終わるタイミングがない【不倫の精算#51】
後ろ指をさされる関係とわかっていても、やめられない不毛なつながり。
不倫を選ぶ女性たちの背景には何があるのか、またこれからどうするのか、垣間見えた胸の内をご紹介します。
「こんな不倫もうやめたいのに」悩みぬく独身女性のため息は
Hさんは40歳、バツイチの独身で実家暮らしをしながら近所のスーパーでパートとして働いていた。
彼女は数年前から年上の既婚男性と不倫関係にあり、「離婚してもらってまで付き合いたいとは思わない」と繰り返すのは聞いていたが、かといって「幸せな不倫」というわけでもなさそうだった。
「もうやめたい」
その夜、別の用事で会う約束をして向かった居酒屋で、ビールのジョッキを握ったままHさんが言った。
「やめればいいじゃん」
枝豆を口に放り込みながら返すと、眉根を寄せた顔でこちらを見たHさんは、
「それができれば苦労はしないのよ……」
と大きなため息をついた。
少しふくよかな体型で血色のいい肌色、スカート一辺倒だが今夜は新しいパンプスが目を引くHさんは、先ほどまで真面目な表情で仕事について話していた。
こちらがお願いした取材だったが、バツイチ女性の仕事について自身の考えを語る姿は年齢より若い印象を与えて、それは心の持ちようが前向きだからだと感じた。
だが、仕事ではない恋愛で抱える現実は先の見えない不倫であり、そのギャップに今さらながらストレスの大きさが伝わった。
「どうやって終わればいいのよ」
泡の消えたジョッキを覗き込んで、Hさんの口から感慨のこもらないつぶやきが漏れた。
案外と絶望的な、「終わるきっかけ」のない関係
「連絡を断てばいい」
「LINEも電話も全部ブロックして音信不通になればいい」
こんなありきたりな言葉はとうの昔に出していて、それができないのが彼女の本音なのだと知っているので、アドバイスはなかった。
「あなたが飽きるまで、かもねえ」
それしかないだろうと思い言葉を返すと、「そうよね」と頷いてHさんはジョッキを口に運ぶ。
「いつか飽きるわよね、こんな関係」
酔いが回って赤くなった頬を見つめながら、まあそんな気配はまったくないが、と思ったが黙っていた。
彼女の不倫は、終わるきっかけがない。
不倫相手の既婚男性と少し不穏な空気が生まれると、Hさんのほうから歩み寄る。
「ワガママは言わない」が暗黙のルールであり、それをHさんが破るとすぐに既婚男性は離れる素振りを見せる。
一方で既婚男性のほうは「時間ができたから」と突然誘いをかけたり逆に予定より早く帰りたがったり、それに彼女が不満を見せれば「じゃあもうやめようか」と簡単に引き下がる姿を出しては主導権を握りたがっていた。
「仕方ないじゃない」と言いながらそんな既婚男性のやり方に従う彼女は、自分の意思で関係をコントロールすることを忘れていた。
「どうやって終わればいいのよ」という言葉が出る時点で、依存しているのは彼女のほうなのだった。
教えて。不倫をやめられない「本当の理由」って、いったい何なの?
「最近は会えているの?」
そう尋ねると、
「うん、先週の金曜日にホテルに行った。
あの人、50前なのにまだまだ元気でね、ご飯を食べた後だったせいか私もがんばっちゃった」
と、ジョッキを持ち上げてケラケラと笑う姿は、さっきとはまた変わっている。
終わりたいと願うのと同じ心で、その男性との肉体関係も楽しんでいるのだった。
話を聞くたびに芽生えるその違和感は、Hさんが既婚男性の何に執着しているのかの疑問を呼ぶ。
「ほかの人じゃダメなの?」
ふと思いついて質問を投げると、Hさんは驚いた顔でこちらを見た。
「え、今さら別の人なんて、無理よ。
いろいろと慣れているし、新しい人を見つけるほうが大変でしょう。
カラダの相性もいいし」
最後の言葉だけ、茶化す口調に変えて答える。
「そっか。
じゃあ、まだまだ飽きないね」
こちらも笑いながらそう返すと、
「飽きてもおかしくない回数なんだけどね。
ホント、どうやったらやめられるのだろうね」
Hさんはドリンクのメニュー表を手に取りながら言った。
こうして最初の言葉に戻るのが、彼女の不倫話を聞くときの常だった。
独身女性が離れがたくなる既婚男性の「手口」って?
Hさんが今の不倫相手と出会ったのは、会社だった。
あるイベントでコンタクトを取った会社のスタッフにいた既婚の彼は、わからないことをまっすぐに確認して現場でもてきぱきと動くHさんを見て、「パートなんてもったいない」と言ったそうだ。
会社の上司からも同じことを言われたことがあったHさんは、外の人間にも認められたことがうれしくて、また彼が「その場限りのつながりの人」だったこともあり、気安く接していたという。
会社を通さない個人的なやり取りとしてLINEのID交換を持ちかけたのは彼のほうで、その頃には業務以外の話もたくさん打ち明けていた彼女は、何の疑いもなくOKした。
イベントは無事に成功し、合同で開いた飲み会で「ふたりだけで二次会をやろう」と彼に誘われたHさんは、「酔った頭で特に何も考えられず」ついていき、そのままホテルに入った。
不倫が始まるよくある流れで、彼女が「手を出しても大丈夫な独身女性」と思われたことはすぐに想像できた。
その可能性はHさん自身もわかっていたが、彼の誘いを断らなかったのは「男性に求められる自分」が見たかったからだ。
相手が既婚者であっても、恋愛のような甘い雰囲気を持ちかけてくれる男性の存在は、離婚して5年、誰とも付き合ってこなかったHさんには貴重だった。
抵抗を失った独身女性。流れる先に「きちんと用意してあった」ワナ
そんな情報もつかんでいた既婚男性は、「抗えない刺激」を用意した。
褒めていい気分にさせ、情を引き出し、カラダに欲を持たせる。
ホテルに入り、土壇場になって「不倫になるけど」としっかり断りを入れることも忘れない既婚男性の周到さは、慣れていることを思わせた。
それでも、乗ってしまったら後は落ちていくだけで、最初から主導権を握られたような形で、Hさんの不倫は続いていた。
「どうやって終わればいいのよ」
の言葉は、応えた側である自分から行動を起こすことへの畏怖があった。
その気持ちに気づいているから、彼は自分の要求に応えない彼女を見るとすぐ「もうやめようか」を持ち出せる。
自分との肉体関係に溺れて「別れたくない」と思っている彼女の心を見抜き、快楽をエサに都合よく扱っているにすぎなかった。
「いつ飽きるのかしらね」
レモンのチューハイを店員さんから受け取って、Hさんが軽い調子でつぶやく。
先のない関係に身を置き、既婚男性に振り回される自分への抵抗は、とうになくしていた。
さっきからちらちらと視線を送る先には自分のスマートフォンがあり、たまにあるという「週末突然のお誘い」を気にかけているのはすぐにわかった。
「あなた次第だろうね」
彼女の前に焼き鳥の乗った皿を進めながら、同じく何でもないような口ぶりで返した。
男性側にばっかり有利。不明瞭で都合のいい、「飽きるまで」
「あなた、最近冷たいよね」
焼き鳥を頬張って、Hさんが不意に言った。
「え?」
「前はもっと親身になってくれたのにさ」
串を皿に置いて、Hさんは拗ねたような表情でこちらを見る。
「だって」
自分のチューハイに視線を投げながら、
「終わらせたくないってわかるからさ」
と、目を合わせないように気をつけながら答えた。
「……」
Hさんは黙る。
これを言うと、彼女はいつもテンションが下がる。
他人に本音を見抜かれる居心地の悪さは、自分の振る舞いが原因だとわかる程度には、理性があった。
「だから、飽きるまでよ」
薄く作ってもらった緑茶のチューハイを一口含んでそう言うと、喉の奥にじわりと刺激が広がった。
「自分で決められないなら、流れに任せるしかないじゃない」
彼女が求めていない「結論」だとしても、不明瞭で都合よく使えるのが「飽きるまで」であり、まだまだそれは遠い、と改めて感じた。
「……」
Hさんは黙る。
不倫に翻弄される自分にまとわりつく虚無感が、下げた肩先からふと漂うようだった。
『不倫の清算』ひろたかおり・著 1200円(10%税込)/主婦の友社
*キンドルアンリミテッド会員なら無料でご覧いただけます
続きを読む
スポンサーリンク