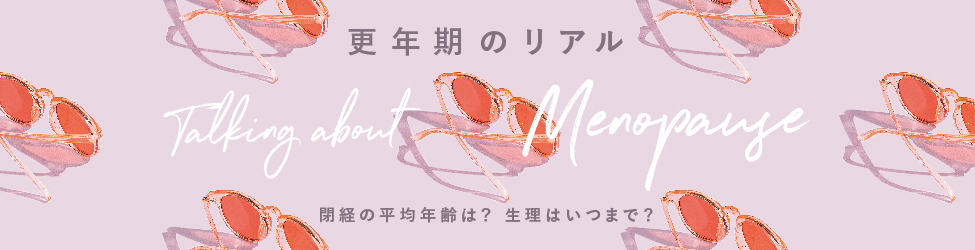「なんで私だけ、夫も乳房も子宮も亡くすのか」自死遺族・がんサバイバーが今となって「伝えたいこと」
自死遺族であり、乳がんサバイバーでもある三井祐子さん。そのあまりにも波乱に満ちた半生は「ひとときたりとも安寧の瞬間がなかったのではないか」とも思えるほど。三井さんにとってのグリーフとケアを伺います。
前編記事『「いちばん辛い言葉は『いい旦那さんだったのにね』でした」自死遺族・乳がんサバイバーの彼女が立ち直れた「きっかけ」』に続く後編です。
夫の闘病の影で、自分自身も4年に渡り乳がんの闘病を続けていた

映画『グリーフケアの時代に』舞台挨拶。
「私が39歳、息子が6年生で娘が1年生のときに乳がんが発覚しました。娘が生まれてすぐに腫瘍が見つかり、乳腺外科では良性の腫瘍と診断されていました。体質的に乳腺症が強すぎて悪性所見が見つけにくいため、1年に1回精密検査を続けていましたが、7年目になって今年は大丈夫とは答えられないなと言われて。どういうことですかと聞いたら、もう少し詳しく検査する必要が出たと」
見つかったのは、乳管内の非浸潤がんでした。右乳房全体に広がった状態のため温存は望めず、保険適用になったばかりの乳房再建を39歳のうちに同時再建で受けました。術後は3か月に1回検診を受けていましたが、4年後の43歳、今度は左乳房のがんが見つかります。このときはステージ1ながら浸潤していたため、全部切除して同時再建となりました。ご主人の自死が起きたのはこの左乳房の3回目の再建手術を待つ間でした。
「抗がん剤治療はまぬがれましたが、左は浸潤がんだったのでホルモン療法となり、術後にタモキシフェンの投与を始めました。今年で6年めです。お薬を飲んでも生理は止まらず、女性ホルモン値も減っていないため更年期症状もなく、6年間副作用も特に感じずに過ごしてきました。が、途中で卵巣にも腫瘍ができてしまって」
不正出血で地元の飛騨高山の病院に駆け込んだところ、卵巣が肥大しているうえに腫瘍があり、子宮にもポリープができています。がんなのかは切除してみないとわからないため、「この際摘出しましょう」と言われました。このように身体の一部を喪失することは死と並ぶグリーフですが、多くの場合は命との天秤になるため決断に長い時間は与えられません。
「乳がんのときはとにかく命が最優先でしたから、迷わずに乳房も切除してくださいと言えたし、運よく再建もしてもらえました。でも、乳房に加えて子宮と卵巣までとなると……私はすぐには返事ができませんでした。47歳でした」
両乳房につづき、卵巣と子宮まで全摘。なんで私だけ、女性性も夫も全部取られるのか

娘さんと2人で。
「夫もすでに世を去り、なんで私ばっかり何でもかんでも取られるのか。身体の内側の女性性まで取られてしまう、この理不尽さと喪失感にはさすがに気持ちの折り合いがつくわけがなく、手術を決める当日もまだ全摘するのかどうかを迷っていました。私の場合はタモキシフェンを飲んでも生理が順調にきていたため、卵巣を摘出すれば一気に女性ホルモン値が下がり、更年期障害が始まるることも明白でした。でも、そうやって悩み抜く私に、娘がひとこと後押ししてくれたのです」
お母さん、女性部位を全部なくすことで女性か女性じゃないかを決めるのはおかしいよ。だって、アンジェリーナ・ジョリーはがんを予防するために乳房と卵巣を全切除したけれど、彼女はまったく変わらず美しいでしょう? 女性の美しさは外見や身体で判断できないよ、人としてどうあるか、女性としてどう生きているかが大事なんじゃないのかな。どんなお母さんでも輝ける場所が必ずあるよ。
「本来は母親が娘を励ますような言葉ですよね(笑)。でも、こうして娘に背中を押してもらって、もう号泣しながら全摘を決断しました」
私はこれから、内面で勝負できるような生き方をするから、子宮も卵巣もなくていい、そう決意しましたが、ここから一気に更年期障害が始まります。
「乳がんの治療でエストロゲン感受性が陽性の私は、女性ホルモンを補充することができません。既往症がなければ補充ができますが、私はいきなりゼロになった女性ホルモンに身体が慣れるのを待つしかない。一般的な闘病とはまた違う戦いが始まりました」
ホットフラッシュ、感情の起伏、ちょっとした言葉でどん底に落ちるメンタル、立てないくらいのめまい。
「できることは、まず自分の時間を大切にすることでした。運動を始め、ジムで汗をかき、辛さを忘れる瞬間を作ることからスタートして。夫が亡くなったあとにも立てないくらいのめまいで仕事を休んだ時期がありましたが、今回はそれ以外の症状も積み重なります。正直、こんなにしんどいなら摘出しなければよかったと思いました。でも、16年の間夫と家族のことで必死だった私にとって、この段階で自分のことだけに向き合うのは必要なグリーフのステップだったのでしょうね」
自分の身体と心だけに向き合うことも、また必要なグリーフケアだった
ご主人が世を去ったのは左乳房の再建の3回目の手術を待っているタイミングでした。それまでもあまりご主人に頼るという感覚がなかった三井さんは、「夫も夫で、自分自身が大変すぎて、私に対する思いはどうだったのかという部分もあります」と言います。
「そんな中で最後まで仕事を続けようとして、家族を支えていたのが夫の精一杯の愛情だったのだろうと思います。ですが私の側は平凡に幸せな結婚を思い描いていましたから、こんな人生送りたくなかったという思いが膨れ上がり、最後は離婚してほしいとも口にしていしまいました。私が離婚したいと口にしたらこの男性は死んでしまうだろうという意識はありましたし、何より夫が元気になってくれるのがいちばんの願いでした。そのために自分ができる精一杯をしなければと日々頑張ってきた。ですが夫の闘病16年の最後に私も気力が尽きてしまいました。結局のところ、自分の闘病が大変なときに頼りたい人に頼れなかったということが、もうどうしようもない私の限界、彼にとっての限界で、努力ではどうにもならなかった運命なのだと今では思えます」
いちばんの後悔は当時反抗期まっさかりだった息子さん、そして娘さんからお父さんを「喪わせてしまった」ことでした。
「正直言って、解放されたという思いがなかったと言えばウソになります。でも、とにかく心が苦しい。そんな中、子どもたちの大切なお父さんを亡くしてしまった以上は、この子どもたちを立派に育てるしかないのだという気持ちで自分を奮い立たせて起き上がっていました。3年ほどは毎日何も考えることなく、必死で目の前の仕事をこなしていって」
ご主人の16年の闘病の過程で、ドクターとケンカして転院することもあれば、あまりの行政支援のなさに絶望することもありました。もちろん、いちばん辛かったのは闘病していたご主人ご本人なのですが、でもその訴えと家族の思いは違い、家族もまた苦しむのだと三井さんは言います。
「患者会のつながりを得てみると、どのご家族も苦しんでいました。あのときこうしてあげられればという思いを抱え続け、自分を一生責め続ける。こんなことを夫は望まない、これだけはやめよう、こんな思いをする人が1人でも少なくなればと、自分が苦しみながら生きていくことそのものをやめようと思い至れたのは、もう夫の死から2年も過ぎたあたりでした」
ずっと張りつめていた責任感も限界に達したのでしょう、きっかけもないまま一気に体調を崩した三井さんは、食事もできず夜も眠れず、最後は仕事にも行けなくなり、1か月休職をしました。
「ご飯が食べられないことがこんなに辛いのか。夫はジストニアを発症した後、嚥下ができず、体重も減って、絶望を感じて死を選んだのだと思います。体調が悪いというのがこんなに辛いことなのか。ある日自分を責めるあまり、娘に『お母さんも死んでしまいたいくらい辛い』と口にしてしまってはっとしました。子どもたちにとっては頼れる大人がいない状態です。このままじゃだめだ、絶対ここから抜け出さなきゃ」
悲しみの形を自分で変えようと感が抜いた三井さんですが、何をすれば自分の体調が戻って元気に笑顔を取り戻せるかわからなかったと言います。
「思えば、生まれてから今まで、自分のために生きてきた時間がなかったんです。ましてや結婚後は、ほぼ夫のため、子どものためにすべてを費やしてきました。敢えて『自分のために』と歯をくいしばり、自分が元気になれそうなあらゆることを無理やりやってみました。運動も私にはあっていましたが、なにより、しばらく休止していた患者会が自分にとっての癒しになりました」
コロナ禍で集まることができていなかったがん患者会を再開させたところ、新聞で大きく取り上げてもらえて、講演会の依頼も。
「お話をする際、おしゃれにも気を遣う余裕がなかった自分に気が付いて、ネイルをひさしぶりにやってもらったら、気持ちがとっても上向きになりました。やっとこの段階で、夫は私がずっと自分を責め続けて生きることを望んだわけじゃないな、と思えてきて。自分の経験を誰かのためになるように変えて、夫の生きた人生を他の人の記憶の中で生かしてあげることができるはずという思いに変わりました。少しずつ広がっていく人とのつながりが、こうして私に未来を向いて顔を上げる力を与えてくれたなと感じます」
地元・飛騨高山でがん患者会を運営しながらグリーフと向き合う

主催するがんサポート団体Owlsの公演会で語る三井さん。
「日々の暮らしのなかにはいろいろな喪失があります。どれが大きい小さいということはなく、同じ自分の中ですらその時点の状況で感じ方は変わると思います。私も胸の全切除を迫られたときは、もう結婚もして子どもも大きいからおっぱいをあげることもないからとまったく迷わず、また何もなくなった胸を見ても喪失は感じませんでした。でも、もしかして順番が逆で今全切除だったなら、ものすごく迷っていたかもしれません」
こうしたグリーフは自分の中でも、また他者とも「明かし合う」ことはしても、「私のほうが不幸」「今回のほうがつらい」というような「比べあいはせず、そのまま受け止める」ことが鉄則だと言います。
「がん患者会を主催してきましたが、じつのところさまざまな喪失に直面する人の気持ちを思ったほどにはわかっていなかったのだなって。自分が経験してはじめて、自分の身体性の喪失に伴う悲嘆が理解できました。そう捉えると、これも私がこれからグリーフケアの活動していく上で、これも必要な体験だったのだなと感じ始めました」
三井さんの暮らす飛騨高山には大きな拠点病院がなく、がんに関する団体もありませんでした。
「唯一の患者会が私の主催する『オウルズ』ですが、まだ高校生の子どもを持ってフルタイムで働く私にとって、どうしても優先順位は子ども1位、仕事2位、活動3位と後回しになります。やりたいことはたくさんあるが費やす時間がない、でもタイミングがないといって過ごしていくのかどうなのかという葛藤もありました」
ですが、ここで三井さんの主催する団体には三井さんの体験してきたことがらがこまやかに生きていることがわかります。
「私の会はがんの患者会であり、本来ならばグリーフケアとがん患者会は性質の違うものです。がん患者会は本来、抗がん剤治療の情報交換や不安な気持ちの共有を主とします。でも、私はグリーフとがんを切り離せないんです。がんで亡くなった方のご遺族の参加も、通ってきてくれた子が亡くなるケースもあります。なのでがんの種類は決めず、実際に会ってみんなが対話すことを大事にしています。だって、髪の毛が抜けてしまうことって、本来はとっても大きなグリーフだと思うんです」
癒したいという気持ちがあれば、さまざまな支えがすべてグリーフケアとなり得る

絵の中で夫は元気に生き続ける。大村順さんの「絆画(きずなえ)」。
自身が大きな喪失の連続に翻弄されながらも、ここまでのお話ではどの瞬間も「癒す側」に回っている三井さん。ご自身はどのようにグリーフケアを受けてきたのでしょうか。
「当時私はグリーフケアの概念を知らなかったのですが、夫が亡くなってばたばたと葬儀が終わってすぐ、近所の方がケーキを焼いて持ってきてくれました。そしてこう言うのです。『私も若いころに夫を亡くしたから、三井さんの気持ちがよくわかるよ。おいしいものを食べてよいんだよ。ケーキを焼いたから食べてね』って。夫はもう食べられなくなってしまったのに、私は生きていて、食べていていいのかな。苦しんで死んだ夫のことを考えると私はおいしい楽しいうれしいという感情を封印しないとならないね、と無意識のうちに思ってしまっていましたが、彼女は『食べていいんだよ、食べなよ』と。私に起きていることを察して、ケーキを焼いて持ってきてくれたのですね。他にも、同じ経験を持つ友人が『あったかい布団でゆっくりと寝てね』と言ってくれました。これらの言葉に私がどれだけ救われたことか」
苦しんで苦しんで自分を責める日々、たまたま新聞で「悲しみはのりこえなくていいんだよ、私は乗り越えようとしていたけれど、このままの自分でいてもいいんだよ」という言葉を目にして救われたことも記憶に強く残るそうです。
「もうひとつ、それも大きなケアだったと思うのが『絆画(きずなえ)』でした。亡くなった方の未来を描くアーティスト、大村順さんを前から知っていて、いつか亡くなった仲間たちの絵を描いてもらいたいと思っていたところで夫が亡くなってしまったんです。10日後に大村さんが名古屋から飛騨高山まできてくれて、丁寧に話を聞いて受け入れてくれました。もし夫が生きていたら、本当は元気に働く父でいたかっただろうな……。そんな夫の叶えられなかった願いを絆画として叶えてもらえました。これも私にとってのグリーフケアでした。絵に込められた魂に触れて、私は穏やかな気持ちになれました。こういうお父さんであってほしかったという私の気持ちがかなえられて」
周囲から受けたこのようなそれぞれの形のケア一つ一つを、三井さんは起き上がることもできないような悲しみの日々の中で鮮明に覚えていると言います。
「こうしたことががん患者に対して、またあらゆるグリーフをかかえる人たちに対して当たり前にできるような地域や社会になっていけば、敢えて行うグリーフケアはいらなくなるかもしれません。日々は喪失の連続で、人は誰でも心にグリーフを抱えています。より大きな悲しみを抱えた人たちがもっと生きやすくなっていく社会を作っていくことができる、それを知ってもらうことが私の役割だと思っています」
「役割」と捉えるようになって以来、三井さんは自身に起きたあまりのグリーフの連続を「それもまた自分にとっては必要な経験だったな」と受け止めることが徐々にできるようになってきたと言います。グリーフがつないでくれるご縁、がんがつないでくれるご縁というものがあり、それもまた自分にとっての糧であるというのです。
「なくしたものの多い人生でしたが、かといってなくしたものばかりでは決してない。むしろ与えられたもののほうが多いかもしれない。夫を忘れる必要はない、夫とともに生きる手段がこの、自分のグリーフを癒しながら生きていくことなのではないかと思うんです。家族3人進む道が違っても、それぞれが心の中に夫を包みこんだまま、自分らしく生きていくことこそが、夫に永遠の生命を与えることなのだと今は考えています」
いま、喪失に苦しみ自分を責め続けている人たちに対して、「こんな生き方をしていんだ」と気づいてもらう恩送りをしたいと語る三井さん。
「2度の自死遺族であり、またがんサバイバーであり、喪失の大きな人生にいつでも翻弄されてきましたが、そんな中でも私の子ども2人はそれぞれ夢や目標を持って生きていける子どもになりました。子どもたちは母が泣いている姿をとても不安に思ったことでしょう。お父さんはああいう形で死んでしまったけれどお母さんは絶対大丈夫。人の命には必ず終わりがくるけれど、でも人は自分の意思で自分の人生を生きていくこともできるのです」
前編>>>「いちばん辛い言葉は『いい旦那さんだったのにね』でした」自死遺族・乳がんサバイバーの彼女が立ち直れた「きっかけ」
スポンサーリンク
【注目の記事】
- 「若作りが痛いオバサン顏」の原因は「黄みがかったブラウン眉」のせい?40・50代が買ってはいけないアイブロウアイテム
- 思春期ど真ん中の高2男子が変わった!ゲームと動画で夜更かし三昧→翌朝起きられない…のダラダラ生活が、スマートウオッチつけたら別人級に
- 40代以降の「肌の変化」どう向き合う? 赤のジェリーでおなじみ「アスタリフト」たった7日試しただけで「わかったこと」とは!
- 【強烈寒波の防寒はコレ!】48歳「冷えに悩む」PTA中受ママが「温活にハマった」結果、家でも外でも「つけっぱなし」!暖房代も節約できるあったかグッズとは?
- 【強烈寒波の防寒はコレ!】48歳「冷えに悩む」PTA中受ママが「温活にハマった」結果、家でも外でも「つけっぱなし」!暖房代も節約できるあったかグッズとは?
スポンサーリンク