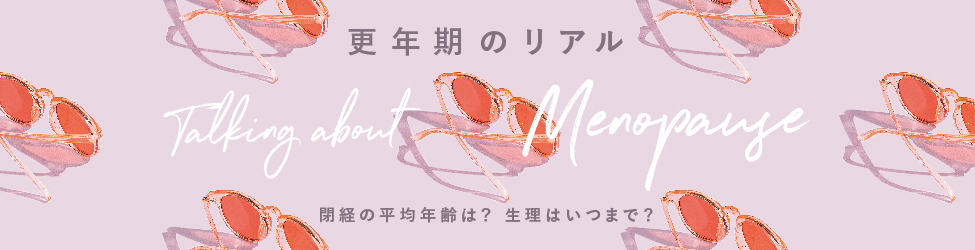土砂が崩れて、道が分断。身動きが取れなくなった母。3人の娘たちと夫と、離れて過ごした震災の夜【能登地震から1年】
天の川が頭上に輝く能登内陸の山あいで、高品質の椎茸栽培を営む日常

澄んだ空気と綺麗な水、豊かな自然に囲まれている柳田(左のビニールハウスは農事組合法人のとっこ)。柳田地区のある能登町は、日本初の世界農業遺産に認定されている。
「街灯も家も少なくて、夜は真っ暗。夏に空を見上げれば、天の川も見えますよ」――朋子さんが暮らすのは能登半島の内陸部・能登町柳田地区。青い空と、山と田んぼの鮮やかな緑がどこまでも続きます。
金沢生まれの朋子さんがこの地で暮らし始めたのは、21年前。

金沢では園芸店に勤務(赤いジャケットが朋子さん)、お花の手入れや寄せ植え作り、ギフトラッピング等の仕事の他、トラックで仕入れにも行っていた。
夫・誠治さんが金沢の大学に通っていた頃から4年間のお付き合いを経て結婚。勤務していた設計事務所を辞めて、誠治さんが農家の2代目として能登町へのIターンを決めたことがきっかけで、柳田に移り住むことに。

子ども達の健やかな成長を祈願して行われる能登地方に伝わる風習”お稚児さん“の行事にて。(2018年、平等寺)
「農事組合法人のとっこ」の代表となった誠治さんは、社員やパート従業員も抱えながら、父が培ってきた椎茸栽培にいそしむ日々。その一方、結婚当初の朋子さんは別の仕事に加え、間もなく授かった長女・次女の出産や育児で大忙し! 当初、椎茸作りにはノータッチでした。
ところが、ある時期から農業に足を踏みいれることに――。

夫・誠治さん(左)と、生前の先代・義父。「私が本格的に椎茸の仕事に関わるようになったのは、お父さんが亡くなった後なので、今になって教えてほしいことがあるんです」と朋子さん。
「9年前に三女を出産して数年経ち、保育園が決まったころでしたね。先代でもある義父が高齢に加えて体調を崩すようになり、思うように仕事ができなくなったんです。
私が徐々に家業を手伝い始めたのはその頃ですが、何より大きな転機になったのは、2019年。義父が亡くなり、夫が大きく気落ちしたんです。全身全霊で椎茸に向き合ってきた父親の偉大さ、相談相手がいなくなったことへの不安……様々な思いに襲われたのでしょうね、初めて弱音を吐くのを聞きました。その時ですね、『夫婦二人三脚でし椎茸作りに向き合おう』と腹を括ったのは」。
そこからの二人の本気は、確かな成果へとつながります。義父が亡くなってわずか3カ月後の2020年2月には、全国996品のキノコが集まる品評会で、『のとっこ』の椎茸が最優秀賞を受賞。それを機に、全国に名の知れた高級すき焼き店や東京の百貨店など、新規取引を次々と獲得します。

誠治さんの作る椎茸が全国の品評会で最優秀賞に。前代の仏前に、夫婦で涙を流しながら報告したのだそう。
さらに、朋子さんならではの視点で新たな試みも――。
「特別興味がない人たちにしてみたら、売り場に並ぶ椎茸ってどれも同じに見えますよね。そこで『のとっこブランド』の差別化を目指して、オリジナルのロゴやパッケージを取り入れたんです。結果的に、様々な販路の拡大につながりました。
それから、『子どもたちが手軽に食べられる椎茸が食卓にあったら』という思いから、ご飯にかけて食べられる『おかずしいたけ』を開発しました。主婦ならではの目線で、ちょっとは貢献できたかな、と思いましたね」。
先代の思いに次代の感性を掛け合わせた結果、事業は徐々に上向きに。お正月をのぞき年間364日もの収穫に追われる毎日は、忙しくも、やりがいに満ちた日々となりつつありました。
そんな充実した日常の合間にようやく巡ってきた1月1日。朋子さん夫婦にとって1年で唯一の休日に襲い掛かったのが、あの能登半島地震でした。
家族5人が3か所でバラバラに。ダンボールをちぎって分け合いながら寒さをしのいだ震災の夜

いつものお正月のように、おせちとお雑煮を食べていた上野さんファミリー。この5時間後に能登地震が発生。
2024年、元日。東京の大学から帰省した長女を迎えた朋子さん夫婦は、久々の家族団らんを味わっていました。
おせち料理を囲んで新年を祝った昼食後、夫・誠治さんは一人でつかの間の外出。一方、朋子さんは「買い物に行きたい」という長女の希望に応え、3人の姉妹とともに車で25分程の距離にある穴水方面に出発します。
「お店に到着して3人の娘を下ろした後、私は年賀状を投函しに車で移動したんです」。
当時、長女は大学1年、次女は高校2年。小学1年生の三女のことも2人に安心して任せることができたという朋子さん。
「いただいた年賀状に対するお返しだったので、早く届けたくて。投函したハガキを当日中に回収してくれるところがいいな、と何か所か巡ってようやく見つけた都合のいいポストに投函し、車に戻ったまさにその瞬間。ものすごい揺れに襲われました」。
その瞬間、「子どもたちのもとに早く戻らないと」という考えがよぎったといいます。ところが――。

震災直後、朋子さんが車内から撮影した土砂崩れの様子。一瞬にして跡形もなく道が塞がれてしまったという。
「振り返ったら、いま通ったばかりの道が土砂でふさがってしまったんです。あたりには土の匂いが広がっていました。今まさに崩れた、その現実を思い知らされるような……そんな強い、圧倒的な匂いでした」。
娘たちのいる店までは、車でたった5分ほど。何とか戻れないかと周りの人に尋ねてみるも、答えは「これが唯一の道だ」という無情なものでした。
「人目もはばからず泣いていた私に、見知らぬ周りの方が『大丈夫、大丈夫』と肩をさすってくれたんです。あの時の励ましで、少し冷静さを取り戻すことができました」。

1年たった今も陥没したままの道路。自宅から作業場に向かうにも、毎日、遠回りしていかねばならない。
そんな中、かろうじて電話が通じ、3人の娘の無事が確認できた朋子さん。
「一旦は安心したものの、娘たちのいた店は天井が落ち、ガラスの破片だらけでそこにはいられない状態だといいます。すると店で周りにいた方が、娘たちも一緒に車に乗せて消防署に避難させてくれるというので、お言葉に甘えてお任せしました。
同時に、『ママはそこに行けないから、今日は別々に過ごそうね』と声をかけました。特にまだ小さい三女のことが心配でしたが――2人の姉が三女の傍にいてくれることは私にとっても心強かったです」。

地震発生直後から近くの消防署に避難した子どもたち(写真は長女)
一方、夫の誠治さんは外出先から踵を返し、手塩にかけて育てている椎茸の栽培ハウスに駆けつけたといいます。すると目の前に広がったのは、傾いたパイプ棚と、そこから地面へと崩れ落ちた無数の菌床ブロックたち――。
大きな動揺こそあれど今すぐできることはないと判断した誠治さんは、朋子さんと娘たちの安否を確認するため穴水方面へとバイクを走らせ始めていました。
「娘たちにはすぐに電話がつながったのに、夫がいる能登町へは電話がまったくつながらない。その状況の差に、余計心配が募りました。ようやく電話が通じたのは、夫のバイクが能登町と穴水の間にある能登空港の付近に差し掛かった頃。距離が近づいたのがよかったのかもしれませんね」。

震災直後の椎茸の栽培ハウス内。折れたパイプや棚から崩れ落ちた菌床ブロックが。
顔は見えずとも、何とかお互いの無事を伝え合うことができた朋子さん一家。家族5人は、3か所に分かれて元日の夜を迎えます。
「夫は地元・柳田の避難所、娘たちは穴水の消防署、私は穴水中学校に身を寄せました。
中学校には、200~300人くらい避難していたでしょうか……。その人数に対して、ストーブは3つだけ。しかもあの夜は、とても冷え込んだんです。周りには自宅から布団や毛布を持参して避難している人も多かったのですが、私の手元には車にあったひざ掛け1枚。近くにあったダンボールをちぎって分け合いながら何とか暖を取ろうとしましたが、結局、寒さで一睡もできませんでしたね」。
スポンサーリンク
【注目の記事】
- 思春期ど真ん中の高2男子が変わった!ゲームと動画で夜更かし三昧→翌朝起きられない…のダラダラ生活が、スマートウオッチつけたら別人級に
- 40代以降の「肌の変化」どう向き合う? 赤のジェリーでおなじみ「アスタリフト」たった7日試しただけで「わかったこと」とは!
- 【強烈寒波の防寒はコレ!】48歳「冷えに悩む」PTA中受ママが「温活にハマった」結果、家でも外でも「つけっぱなし」!暖房代も節約できるあったかグッズとは?
- 【強烈寒波の防寒はコレ!】48歳「冷えに悩む」PTA中受ママが「温活にハマった」結果、家でも外でも「つけっぱなし」!暖房代も節約できるあったかグッズとは?
- 脱・着太りにやっぱり頼れる【ユニクロ】。真冬の屋外イベントも怖くない、防寒と美シルエットを両立したダウンコーデ【40代の毎日コーデ】
スポンサーリンク