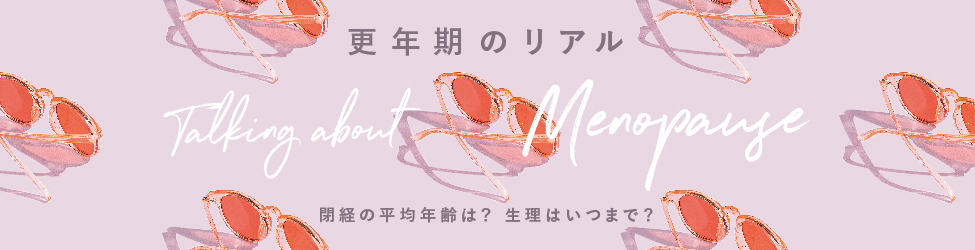報われない愛、救われない幼少期。それでも「美」を描き続けた「喜多川歌麿」の不器用な生き方。染谷将太が「べらぼう」で体現する悲しくも切ない天才絵師の生涯は【NHK大河『べらぼう』第46回】
「苦しみを絵に昇華した歌麿」
「べらぼう」においても歌麿(染谷将太)は大河ドラマらしく大胆な脚色が施されています。
歌麿にとって母(向里祐香)を火の中で見捨てた出来事は不幸の原風景であるものの、唐丸を名乗っていた頃は罪悪感を抱きつつも、屈託なく笑う明るい少年でした。蔦重(横浜流星)の“おまえを当代一の絵師にする”という言葉に胸を躍らせ、未来への希望に満ちていました。
ところが、義父にあたる向こう傷の素浪人(高木勝也)が現れたことで、平穏な日々は一変。歌麿は素浪人に脅され、金をゆすられ、最後にはこの男を川に突き落とし、殺害。母の“あんたは鬼の子”という言葉と罪の重さに押しつぶされ、幸せを諦めました。蔦重と再会するまでは男娼として自らを傷つけることで生き延びていたのです。
笑顔の少年が現実に揉まれる中で心を閉ざしてしまう――それはよくある悲劇です。
蔦重も親なし、家なし、金なしの境遇でしたが、41話「歌麿筆美人大首絵」で、つよ(高岡早紀)から幼名「柯理(からまる)」と呼ばれたときのふと思い出したような表情を見る限り、母の記憶は無意識の層に静かに沈んでいたようですし、明るくおおらかな性格で、常に陽の当たる道を歩いてきたように思います。一方、歌麿は母の愛情を求め続けており、絵師としての才能に恵まれ、蔦重や鳥山石燕(片岡鶴太郎)にかわいがられているものの、まるで一人暗い洞窟を手探りで進んでいるような男だと思います。
しかし、歌麿は絵を描くときだけは別でした。絵は苦しみを解放し、この世界の美しさに気付かせたのです。特に、30話「人まね歌麿」で、石燕から三つ目の使命を改めて告げられた後、庭の草花の生命力を感じ取り、ピンクの花を鮮やかに写し取る姿は多くの視聴者の心を揺さぶったと思います。歌麿は世界の美しさに触れ、穏やかな眼差しで全てを見つめているように見えました。
染谷将太は歌麿を演じるにあたり、常に彼を覆う罪悪感と悲しみ、そして内向性を極めて繊細に表現しています。歌麿の心の苦しみや格闘を全身に滲ませ、深みのある演技を見せてくれています。
▶▶なぜ写楽は10カ月で姿を消したのか。推し活文化が花開いた江戸で生まれた天才の「光と影」に迫る1 2
スポンサーリンク
スポンサーリンク