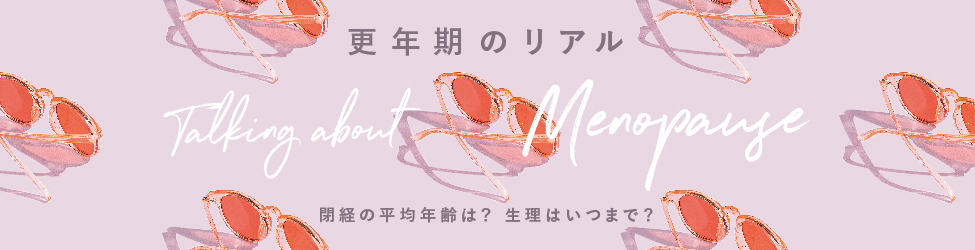「学校に行きたくない」と言い出せなかった不登校児の精一杯のSOS。学校と母への本音【2025年度ベスト記事セレクション】
「自分を押し殺すような毎日だった」――そう言えるのも、大人になった今だから。時間が経って初めて言葉にできることがある
こうして、間もなく登校を再開。とはいえそれは、大きな違和感を抱えつつ、断続的な欠席を差し挟みながら、という状態でした。
「学校は、行きたくない場所。それでも、新しい知識を得たり、教科書を読んだりするのは好き。『学校に行くからには、勉強はしたい』と思っていました」。
そこで、登校したときは通常通り授業に出席。一方で困ったのが、休み時間の過ごし方でした。
「友達とどう過ごしていいのかが、わからなくなってしまったんです。ですから、休み時間は、カウンセラーがいる相談室や、保健室に避難。授業が始まるころ、再び教室に戻って授業を受ける。それを繰り返していました」。
その経験も踏まえて、さゆりさんは改めて、当時の違和感の正体を次のように分析します。
「今だからわかるのですが、『それでもやっぱり行きたくない』という思いの根っこにあったのは、『私の資質や性格と、学校という場のアンマッチ』なんですよね。
私はもともと、良く言えば意志が強くて、悪く言えばわがままなタイプ。たとえば小さい頃は、みんなで『縄跳びで遊ぶ』と決めて外に飛び出して、『やっぱり、私はジャングルジムに行ってもいい?』と言い出す子がいても譲らない。相手を慮ったり、例外を作ったりはせず、『みんなで決めたんだから、今日は縄跳びですっ!』って貫くような子でした。判断は白か黒。グレーをつくれなかったんですよね。
ところが、小学3~4年生くらいから、精神的な発達も手伝って、『周りに合わせないと独りぼっちになっちゃうかな?』と思うことが増えてきました。図書室で本を読みたくても、『外で遊ぼう』と誘われたら、『いいよ』と答える。それが自然に育まれた協調性だったら良かったのですが、私はそのバランスのとり方もわからず、かなり無理をしている状態だったんです。
こうして振り返ると、そもそも集団行動も友達付き合いも得意ではない。ところが、ある時期から、心が欲していない方を選び続けるようになって――自分を押し殺すような感覚が、澱のように積み重なっていたのだと思います」。
スポンサーリンク