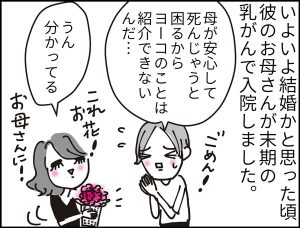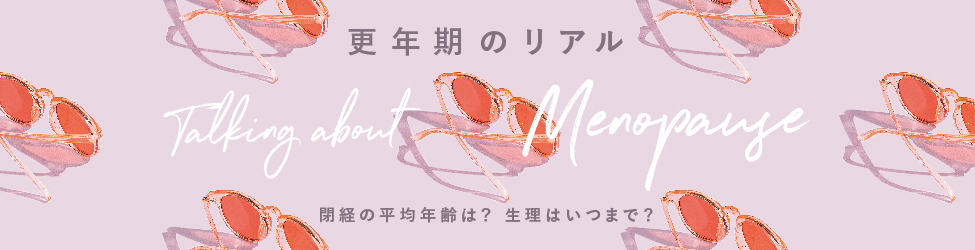あの指が私の身体に触れることを想像するだけでどうにかなってしまう【不倫の精算#46】後編
前編「「体だけの関係だから」と何度も繰り返す彼女。本当にそう思ってる?【不倫の精算#46】前編」の続きです。
後ろ指をさされる関係とわかっていても、やめられない不毛なつながり。
不倫を選ぶ女性たちの背景には何があるのか、またこれからどうするのか、垣間見えた胸の内をご紹介します。
酔った勢いで口にしてしまった。あなたの指が……と
Cさんの不倫相手は40歳、会社の取引先の営業で、以前から顔を合わせることが多かったそうだ。
「結婚している男の人って、自分の家庭を自慢するかいっさい触れないか、どちらかよね」
以前、Cさんは不思議そうに首をかしげながらそう言っていたが、彼は後者で左指のリングだけが既婚の証であり、家庭の状態を口にしないことも、彼女の関心を引き寄せたのかもしれない。
納品が終わって少しの時間に世間話をする程度の距離感だったのが、Cさんが彼に欲を覚えたのは「指」だった。
「色白できれいな肌なのだけど節が太くてね、長さもあって妙に色気があるのよ」
書類をめくるとき、スマートフォンを手に取るとき、ふと髪に触れるとき、彼の指の動きから目が離せなかった、という。
その欲をぶつける場になったのが年度末に合同で開かれた飲み会で、「ワインを飲みすぎちゃって」と言い訳しながらCさんが言うには、彼に「あなたの指は色気があって最高」とストレートに口にしてしまい、同じく酔っていたらしい彼が
「食べてみますか?」
と耳元で囁いてきた瞬間に、彼女は身を委ねることを決めた。
こんなこと、この人とじゃないとできないから
彼が自分と同じようにベッドで加虐性や非加虐性の出現を好むことを知ったのは、その日だったという。
「彼の指をしゃぶっていたらね、『手を縛ってもいいですか?』って。
普通、そういうお願いって恐る恐るするものじゃない?
彼、私の顎をつかみながら普段通りのしゃべり方で言ったのよ」
そしてそれがCさんの扉を開く決定打になり、ふたりは最初から「そっち」のプレイに没頭したそうだ。
「こんなこと、できる人ってなかなかいないじゃない」
Cさんは繰り返しそう言う。
確かに、極端な性癖なら最初から合う人を見つけるのは至難の業で、「この人としかできない」という確信が、Cさんのなかから不倫への後ろめたさを消していた。
その夜のうちにふたりは「ホテル以外で会わない」と約束したそうで、普段の連絡にはLINE以外のコミュニケーションアプリを使い、それも待ち合わせの時間と場所を確認するだけの素っ気ないやり取りであることは、実際に画面を見せられて知っていた。
「彼に恋愛感情はない」
とCさんがあえて言うのは、「普通の不倫」はお互いに恋焦がれて苦しむもの、という認識があるからで、そうじゃない自分、特殊な刺激を楽しむだけの関係と割り切っていることを、客観的に確認したいからだろうなと思った。
だが、望む現実のなかでみずから変わっていったのはCさんだった。
好きという言葉が口をついて出てしまうその瞬間のあなたは
「会えないとき、寂しくないですか?」
以前そう尋ねたときがあったが、Cさんはすぐに
「別に。
そもそも好きなときに会えるような関係じゃないしね」
とあっさり返した。
その様子に嘘や強がりは見えず、当人なりに納得した関係になっているのかと思っていたが、ある日その考えが一変した。
「ねえ、やっている最中に、そうじゃなくても好きって言うよね?」
「は?」
唐突な質問は、「先日彼とプレイを楽しんでいるときに思わず口から出てしまった」そうで、
「こう、勢いで好きとか、言わない?」
と話すCさんの無邪気な姿に言葉をのんだ。
「……」
「言わないの?」
何も答えないこちらに眉をひそめてCさんは重ねて尋ねたが、
「……言わないですね。
好きじゃない人には出ないので」
と慎重に返すと、「そうかしら」と今度は不満そうに口をとがらせた。
心臓が重たい鼓動を打ち出すのを感じた。
その質問自体、40代半ばの女性から出るものじゃないという衝撃と、その言葉が出る自分について違和感を持たない不思議さと、「ああやっぱりこうなった」と目をつぶりたくなるような絶望と、一瞬で気が塞いだ。
「……恋愛感情じゃないのですか」
答えに予想がつくので聞いてはいけないと思ったが、それでも確認せずにいられなかった。
「え?
好きって言ったから?
まさか。
彼のプレイ以外で好きになるところなんて、ないわよ」
あっけらかんと言葉を返すCさんは、「好き」という言葉の重みを、それを口にする自分の姿を、まるで見ていなかった。
認めたくないでしょうね、本当はカレの身体以外も好きって
それ以降、プレイの最中に既婚の彼に好きと言った話は聞かなかったが、代わりに彼女から出るのは「物足りなさ」についてだった。
「終わった後にさ、すぐシャワーに行っちゃうの。
こっちも疲れているし、腕枕くらいしてくれてもいいじゃない?」
「フリータイムが終わるまでまだ時間があるのに、着替えたらすぐ帰ろうとするのって、やっぱり家庭を思い出すのかしらね」
こんな言葉は、彼と不倫関係になった頃には出なかった不満だ。
だが彼女は、そんな変化にも気づいていなかった。
「もっと会いたい」と逢瀬を焦がれるような様子こそなかったが、「年末年始はやっぱり会えないかなあ」とため息をつく姿は、普通の恋愛で彼氏とのデートを心待ちにする女性のそれだった。
「……」
どうして、自覚しないのか。
「不倫は遊び」
「彼氏とはね、好みが合うだけだから」
今夜、何度も耳にしてきた言葉がまったく頭に入らないのは、酔っているせいだけではない、彼女の幼稚さに苛立っているからだと、わかっていた。
考えないままに彼女のなかで育つ「何か」は、いずれ頭を出すだろう。
その正体を目の当たりにしたとき、彼女は自分が口にしてきた言葉の数々が、自分で形作ってきた世界が、壊れることを知るのだ。
「わからないわ。
私、今の彼氏に恋愛感情とか全然ないもの」
この言葉の虚しさは、聞いている側ではない、言った側にこそ重くのしかかる。
Cさんがこれまで、恋愛についてどんな経験をしてきたか、そういえばまったく知らない。聞いていない。話題に出ない。
その意味を、炭酸の泡が揺れるグラスを握りながら考えていた。
*このシリーズの一覧
この記事の前編>>>「体だけの関係だから」と何度も繰り返す彼女。本当にそう思ってる?【不倫の精算#46】前編
続きを読む
スポンサーリンク
【注目の記事】
- 思春期ど真ん中の高2男子が変わった!ゲームと動画で夜更かし三昧→翌朝起きられない…のダラダラ生活が、スマートウオッチつけたら別人級に
- 40代以降の「肌の変化」どう向き合う? 赤のジェリーでおなじみ「アスタリフト」たった7日試しただけで「わかったこと」とは!
- 【強烈寒波の防寒はコレ!】48歳「冷えに悩む」PTA中受ママが「温活にハマった」結果、家でも外でも「つけっぱなし」!暖房代も節約できるあったかグッズとは?
- 【強烈寒波の防寒はコレ!】48歳「冷えに悩む」PTA中受ママが「温活にハマった」結果、家でも外でも「つけっぱなし」!暖房代も節約できるあったかグッズとは?
- 脱・着太りにやっぱり頼れる【ユニクロ】。真冬の屋外イベントも怖くない、防寒と美シルエットを両立したダウンコーデ【40代の毎日コーデ】
スポンサーリンク