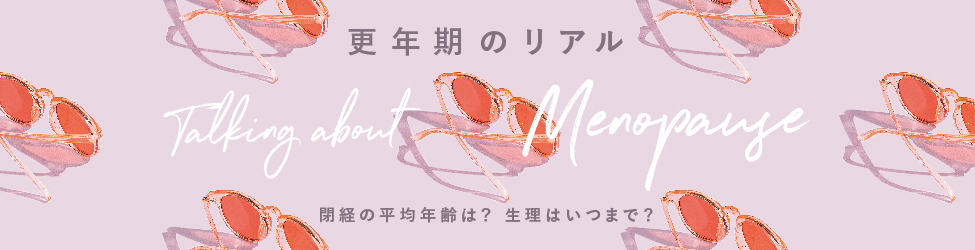恋愛をあきらめていた私に、一回り年下の後輩男子は【小説・あなたのはじめては、わたしのひさしぶり3】
ひとりでいたい
翌朝、私は高坂君を、通勤電車の中で見つけた。
飲み会で、全然自分のことを話さなかったから、彼が私と同じ路線に住んでいることも知らなかったので、見つけた時は、驚いた。
会社に駅が近づくたびに、次第に車内が混んできて、私は彼のすぐ隣に押し出されてしまった。
洗濯したてのような爽やかな香りが、ふわっと入ってくる。
それでも高坂君は、私に気づかないで、ずっとスマホに見入っている。
どうやらゲームをしているらしかった。
彼は、全く顔も上げない。
バリアを張って、コミュニケーションを遮断しているかのようだった。
会社の人たちが「なんだアイツ」とぼやいていた無愛想さは、満員電車の中ではあまり目立たない。他の多くの人たちも同じようにうつむいて、スマホに見入っているから。
誰とも話をしたくない、そんな時期が私にもあったのを不意に思い出した。
社内恋愛をしていた彼と別れた頃は、できれば一人でいたかった。
会社の人たちに、話しかけられたくはなかった。
彼とのことを、誰にも聞かれたくなかったし、語りたくなかったから。
ちいさなきっかけ
高坂くんも、誰とも話したくない時期なのかもしれない。
私だって、飲み会に出たくない時もある。
彼が、壊れそうな何かを背負っているような気がするのは、私だけなんだろうか。
彼は、嘘つきではない。
部長に聞かれたら「彼女はいません」と素直に答えていた。
ただ、人間付き合いが苦手なだけかもしれない。
私は、彼のことを、なんだアイツ、とは思えなかった。
彼が、プードルの画像を待ち受けにしていたからかもしれない。
居酒屋で、彼が落としたスマートフォンの待ち受けには、白くてふわふわの犬が映っていた。
「かわいい!もしかしてプードル?」
と聞いたら、そうです、と答えてくれた。
実家で飼っているのだと。
私の実家もプードル飼ってるの、と言ったら、そうなんですか、と、あの時、少しだけ、笑った気がした。
私は急いで自分のスマートフォンのアルバムに入っている、実家のプードルの画像を探し出す。
犬の話だったら、弾むかもしれない。
でも、すぐ隣で指を動かす私に、彼は気づかない。
しかたなく、小声で話しかける。
新しいともだち
「……高坂くん」
「えっ!?」
彼は、目をむいて私を見た。
「な、なんでここにいるんですか!?」
「さっきからいるんだけど。私、桜道駅だから」
「マジですか? 僕もですよ」
「本当に? ねえ、ところでうちのプードル……」
そこまで言いかけた時に、急ブレーキがかかり、みんなが一斉によろけ、私も倒れそうになったけれど、必死に踏ん張った。
「これ」
彼が、何かを差し出してくる。
男物の長傘だった。
「体に掴まられるのは抵抗あるけど、傘なら、いいですよ」
ひとこと余計な気がしたけれど、ありがたく傘の持ち手を握らせてもらう。
彼は、私が握りやすいような位置で、傘の真ん中あたりを持っていてくれる。おかげで、電車が次に揺れた時は、もうよろけないで済んだ。
彼は、優しい。多分、優しさを表に出していないだけなのだろう。
そっと高坂くんの顔を見上げる。
照れくさいのか、彼は窓の外を見つめている。
私の視線に気づいているのかどうかも、わからない。
高坂くんは、綺麗な肌をしていた。
28歳。私よりもひとまわりも違うから、本当に若い。
インドア派なのか、日焼けもしていない色白の肌は、うらやましいほどしっとりしていた。
「ねえ、後でうちの実家のプードルの画像も見てくれる?」
彼は、窓の外を見つめたまま、小さく頷いた。
「じゃあ、後でLINE交換しよう? 画像送るから」
彼はまた頷いた。その日の昼過ぎ、私のLINEに1人、新しい友達が追加された。
スポンサーリンク
【注目の記事】
- 思春期ど真ん中の高2男子が変わった!ゲームと動画で夜更かし三昧→翌朝起きられない…のダラダラ生活が、スマートウオッチつけたら別人級に
- 40代以降の「肌の変化」どう向き合う? 赤のジェリーでおなじみ「アスタリフト」たった7日試しただけで「わかったこと」とは!
- 【強烈寒波の防寒はコレ!】48歳「冷えに悩む」PTA中受ママが「温活にハマった」結果、家でも外でも「つけっぱなし」!暖房代も節約できるあったかグッズとは?
- 【強烈寒波の防寒はコレ!】48歳「冷えに悩む」PTA中受ママが「温活にハマった」結果、家でも外でも「つけっぱなし」!暖房代も節約できるあったかグッズとは?
- 脱・着太りにやっぱり頼れる【ユニクロ】。真冬の屋外イベントも怖くない、防寒と美シルエットを両立したダウンコーデ【40代の毎日コーデ】
スポンサーリンク