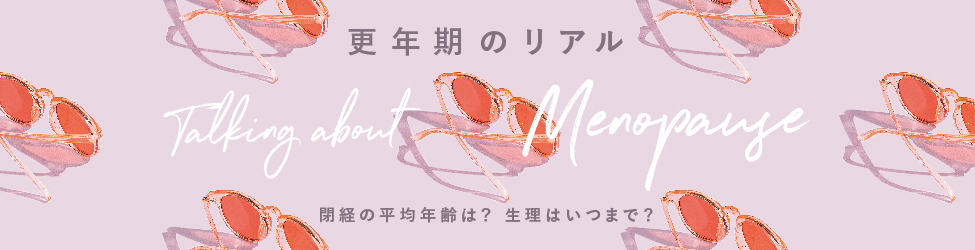「やっぱり、ほっとけないし」年下男子の言葉にドキドキ【年下小説・あなわた#9】
【小説・あなたのはじめては、わたしのひさしぶり vol.9】
長い間ひとりで過ごしていた私の部署に、年下の男性が配属されてきた。歓迎会に誘っても「そういうの迷惑なんですよね」と言い放つ、協調性のない若い男の子。ところが、あるとき共通の趣味「犬好き」に気づき、2人の関係に少しずつ変化が。
誰かといること
高坂くんとは、犬カフェを出て直ぐのところでお別れしようとした。
けれど、彼が「せっかく良く知らない街に来たんだし、少し周りを散歩しましょうよ」と言ってきたので、それもいいかなと思って、さらに一緒にいることになった。
本当は少し、疲れ始めていたのだけれど。
久しぶりに男の人と二人で行動を共にしている。
つまり、これはデートみたいなものなのかもしれない。
高坂くんは会社の同僚で、年齢も一回りも下で。
デートだなんて言ったら、彼がびっくりしてしまうかもしれないけれど。
高坂くんは、女の人と出かけるのが、本当に初めてらしかった。
一人で先にスタスタと歩いて行ってしまい、私が早足で慌ててついていくことが多かったし、女の人の足に合わせようだなんて考えてもいないようだった。
それに、全然休もうとしない。
年が上で、普段あまり歩かない私はすぐに音を上げて、ちょっと座りたい、なんて言い出してしまった。
お願いさえすれば、彼は素直にそれを叶えてはくれるのだけど。
不思議な安心感
駅前の商店街を散歩し、突き当たりにあった公園で少し休んだ。
高坂くんと私はベンチに座ったけれど、間に人がもう一人座れそうなほど、スペースが空いてしまう。
恋人でもないのだから、そんなにくっつくわけにもいかない。
だけど、あまりにも離れすぎているような気もして、落ち着かなかった。
どのくらいの距離を空けるのがちょうどいいのか、私にももう、よくわからなくなっていた。
異性とベンチに並んで座るなんて、長いことしていない。
高坂くんは、寄ってくるハトをぼんやり眺めている。
私はそんな高坂くんをぼうっと見つめていた。
もっと近くに行きたいかと聞かれたら、別に行かなくてもいい。
でも、そばに、彼がいてくれることに、不思議な安心感があった。
「こういうの、楽しい?」
「楽しいって、何がですか?」
「こうやってお出かけすること」
「ああ」
高坂くんは少し考えて、
「まあ、たまにはこういうのも、面白いですね」
とだけ答えた。
彼のはじめて
たまたま、お互いに、犬が好きだったから。
私と高坂くんは、ただそんな理由で、今日、週末を一緒に過ごした。
もう次の約束も何もない。
今日だけ一緒に出かけただけなのに、私はいちいち彼の言葉や態度に緊張している。
「あの子たち、新しいお家が見つかるといいね」
どうしても私たちは、犬の話ばかりしてしまう。
「そうですね」
高坂くんも頷いた。
「やっぱ、気になりますよね、どうなっちゃうのか」
私は頷き、また黙った。
高坂くんが隣にいる。
ただそれだけで、とても幸せな気持ちになっている自分がいた。
彼のことが好きだからなのか、それはよくわからない。
でも、私とこうやって出かけてくれる男の人が現れたことが、ありがたかった。
ずっと満たされていなくて、隣に誰もいない週末を過ごしていたから、こんなにも心地いいものなんだなと思い知らされている。
「まあ、また見に行きましょうよ」
高坂くんはそう言って、立ち上がった。
そして、私に背中を向けたまま、こう続けた。
「やっぱ、あいつらのこと、ほっとけないですし」
スポンサーリンク
【注目の記事】
スポンサーリンク