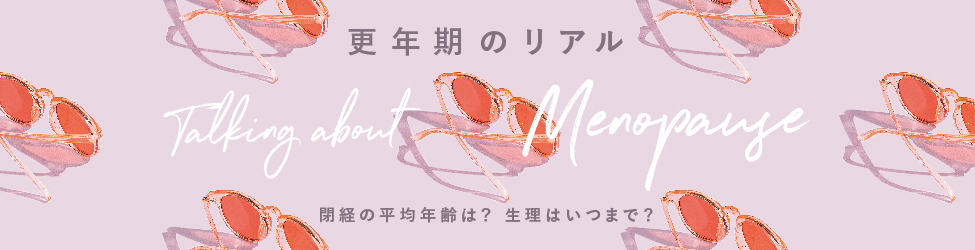「あれ、2人で同棲してるの?」カレが否定しないとき【あなわた#11】
【小説・あなたのはじめては、わたしのひさしぶり vol.11】
これまでの話
長い間ひとりで過ごしていた私の部署に、年下の男性が配属されてきた。歓迎会に誘っても「そういうの迷惑なんですよね」と言い放つ、協調性のない若い男の子、高坂くん。ところが、ひょんなことから共通の趣味「犬好き」に気づく。女性と2人で出かけたことすらなかったピュアな高坂くんと、私の関係は、少しずつ変化し……。
ひろがる輪
「また来週も、一緒に出かけませんか?」
高坂くんにそう誘われて、私はどきっとした。
毎週2人で出かけるなんて、まるで私たちは付き合っているみたいだ。
付き合うだなんて、もう、遠い昔のことすぎて、どんな状態が付き合っているというもののかどうかも、今ではもう、よくわからない。
でも、毎週末を一緒に過ごすようになったら、なんだかそれは、かなり恋人に近い状態なんじゃないだろうか。
お互いにとても犬が好きで、そして、お互いに犬が飼えない部屋に住んでいて。
私たちの共通項なんて、多分、それだけだ。
ただ犬が好きなだけで、高坂くんの気持ちは先走っている。
そして私をそれに巻き込んでいる。
別に、私のことを好きだとか、私と一緒にいたいとかではない。
きっと彼は、犬が好きで、犬と一緒にいたいだけなのだ。
それでも私は構わなかった。
私だって、犬が好きで、犬と一緒にいたかったから。
そして、そこに、高坂くんがいてくれたら、もっと楽しいだろうから。
交わす目と目
結局、週末は、私は高坂くんと2人きりで過ごすことはなかった。
ドッグカフェに向かったのが、私と高坂くん以外にあと2人いたからだ。
彼が見せた犬の画像を見て、直接会ってみたいと言ってくれた会社の人が2人、同行したのだ。
里親を探している犬にとっては、とてもありがたい話だった。
みんな可愛くておとなしいし、早くいい家族に巡り会えてほしい。
だから、カフェに見に来てくれる人は、多いほうが、いい。
それなのに、少しだけ私はがっかりしている。
高坂くんとふたりで、デートみたいに、今日も過ごせるのかなと思っていたから……。
ドッグカフェのスタッフさんは、私たちのことを覚えていてくれた。
「この間、ペットフードも届きました。たくさんいただいちゃって、ありがとうございました」
挨拶されている私たちを、同僚の2人は不思議そうに見つめている。
「ひょっとして2人は一緒に暮らしてるの?」
そう聞かれて、私は思わず高坂くんを見た。
彼も、私を見ていた。
私たちの目と目が合って、不思議な時間が流れた。
ふたりきりの時間
私たちが同棲していると思われたのは、2人同時に駅の改札に現れたからだ。
「違いますよ、偶然、同じ駅に住んでるだけなんです」
慌てて否定する私の横で、高坂くんは何も言わない。
「でも付き合ってるの?」
「付き合ってないですよ〜」
まだ、高坂くんは、黙っている。
私だけが、一所懸命、否定していた。
「……さっきはすみません」
帰り道、2人で同じ駅のホームに降り立った時に、高坂くんが小さな声でそう言った。
「さっきって?」
「その、付き合ってるかと聞かれた時、何も、言えなくて」
高坂くんは口ごもっている。
「ああいう時、どう言ったらいいのか全然わからなくて。まかせちゃってすみませんでした」
「大丈夫よ」
私は微笑んだ。
高坂くんは、恋人がいたことがない。
男と女のいろいろなイベントを何も知らないのだ。
そんな彼が、私と一緒にいる。
それだけで、今は、満足だった、はずなのに……。
スポンサーリンク
【注目の記事】
スポンサーリンク