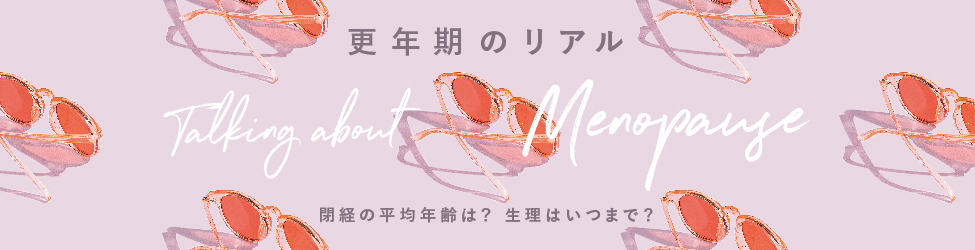40歳になっても私は恋愛に不器用なままで【年下小説・あなわた#16】
おひとりさま40代の私の部署に、年下の男性が配属されてきた。 歓迎会に誘っても「そういうの迷惑なんですよね」と言い放つ、協調性のない若い男の子、高坂くん。 ところが、ひょんなことからお互い「犬が好き」なことに気づく。 女性と2人で出かけたことすらなかったピュアな高坂くんと、私の関係は、少しずつ変化し……。
もしかして会えたら。
週末、私はいつものようにドッグカフェに向かった。
もう何度も高坂くんと通っていたから、足が自然に向いてしまったのではない。
もしかしたら、ドッグカフェに行ったら、彼に会えるかもしれない。
そんな淡い期待があったから、出かけてしまったのだ。
お昼過ぎに、ドッグカフェのある駅に降り立ち、あたりを見回す。
ひょっとしたら、高坂くんが同じ電車から降りてくるかもしれない。
でも、そんなことはなかった。
隣に誰もいない、たった一人の週末は、とても心細い。
いつの間にか、私の中では高坂くんがこんなにも大きな存在を占めるようになっていた。
ドッグカフェは、いつもよりも遠く感じた。
高坂くんと話をしながら進む道は、着いてしまうのが早すぎるくらいだったのに。
ただ、昔の彼のことを、反射的に隠した。
それだけで、こんなにも気まずく、彼との間には沈黙が続いている。
彼がいない場所
ドッグカフェの扉を開けると、何匹もの犬が出迎えてくれた。
何度も言ったから、私を覚えてくれている犬もいて、嬉しそうにゲージの向こうでジャンプして、早く抱っこして、と催促している。
ここは、里親探しをしている犬たちがいるドッグカフェ。
いろいろな事情で飼い主が手放さざるをえなくなった犬たちが、新しい家族を探している。
だからここに来るたびに、先週いた犬のうち何匹かの姿がなくなっている。
誰かが引き取っていったのだ。そしてその代わりに新しい犬が何匹か入ってきている。
このカフェはそうやって少しずつ顔ぶれが変わっていくところだった。
私は店の中を祈るような気持ちで見回した。
ここだったら、犬好きな高坂くんは、気持ちを開いてにこやかにしている。
ここでだったら、彼と仲直りができる気がしていた。
だけど、彼の姿はなかった。
一気に気持ちが沈んでいく。
休日の過ごしかた
元気なく店内の椅子に腰を下ろした私を、犬たちが取り囲み、手のひらを舐めたり、膝に飛び乗ってこようとしている。
可愛い犬たちのおかげで、心が少しずつ癒されていく。
高坂くんのことで、一喜一憂するだけの毎日なんて、情けない。
私が犬のためにできることだってきっといっぱいある。
仕事だってやらなくちゃならないことが、たくさんある。
彼のことで落ち込んでばかりは、いられないのだから。
40歳になっても、私は恋愛に不器用なままで、ちょっとしたことで相手をがっかりさせてしまって、せっかく育ち始めていた素敵な関係を台無しにしてしまう。
何度、同じような失敗を繰り返せばいいのだろう。
情けないけれど、でも、もう起きたことは、取り返せない。
私は膝の上の真っ白なプードルの頭を撫でながら、少しずつ、気持ちを前に持って行こうとした。
その時だった。
何匹もの犬の吠え声と共に、カフェの扉が開いた。
「ただいま戻りました!」
その声をした方を見ると、そこには、高坂くんがいた。
彼の手には何本ものリードが握られていて、彼の足元には数匹の小型犬がまとわりついていた。
スポンサーリンク
【注目の記事】
- 思春期ど真ん中の高2男子が変わった!ゲームと動画で夜更かし三昧→翌朝起きられない…のダラダラ生活が、スマートウオッチつけたら別人級に
- 40代以降の「肌の変化」どう向き合う? 赤のジェリーでおなじみ「アスタリフト」たった7日試しただけで「わかったこと」とは!
- 【強烈寒波の防寒はコレ!】48歳「冷えに悩む」PTA中受ママが「温活にハマった」結果、家でも外でも「つけっぱなし」!暖房代も節約できるあったかグッズとは?
- 【強烈寒波の防寒はコレ!】48歳「冷えに悩む」PTA中受ママが「温活にハマった」結果、家でも外でも「つけっぱなし」!暖房代も節約できるあったかグッズとは?
- 脱・着太りにやっぱり頼れる【ユニクロ】。真冬の屋外イベントも怖くない、防寒と美シルエットを両立したダウンコーデ【40代の毎日コーデ】
スポンサーリンク