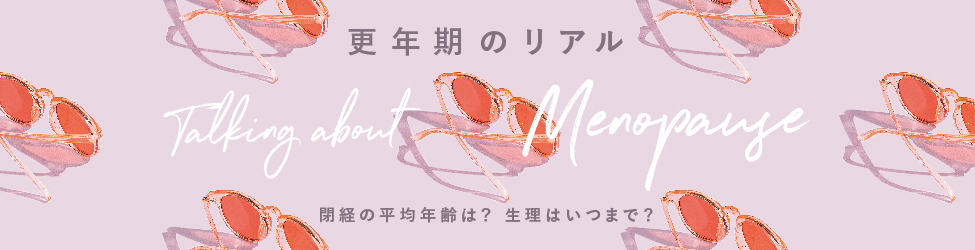わが子の死、ペットとの別れ、震災で故郷を失う。すべての悲嘆を等しく分かち合う「グリーフケア」がいま必要である理由
「グリーフケア」という言葉をご存じでしょうか。グリーフは直訳すれば「悲嘆」、さまざまな「喪失」の体験に伴う悲嘆をケアしていく動きのことです。大切な人やペットの喪失のほか、財産・仕事の喪失、いじめやハラスメントによる自尊心の喪失など具体的な喪失のある体験のほか、喪失そのものが不確実な「あいまいな喪失」、たとえば原発事故で故郷に帰れない、別れはないものの認知症で関係性を失うなどの体験も対象とします。
トラウマとは何が違うの?とも聞かれますが、グリーフの背景にあるものは愛情・愛着である一方、トラウマの背景は恐怖・脅威だとも説明されます。
このグリーフケアをテーマとしたドキュメンタリー映画『グリーフケアの時代に』が12月1日より全国公開されます。監督の中村裕さんに「なぜいまグリーフケアを取り上げたのか」お話を伺いました。
【画像】映画『グリーフケアの時代に』出演者の皆さん
「グリーフケアとはどのような言葉なのか?」知らないところから取材は始まった
――中村監督は、長い間取材を続けた瀬戸内寂聴先生を2021年に「喪失」なさっています。その経緯でグリーフケアにご興味を持っての企画でしょうか?
いいえ、グリーフケアという言葉も概念も、まったく知りませんでした。ぼくはドキュメンタリーのディレクターとして瀬戸内寂聴先生を17年に渡って撮影し続けました。2021年9月に先生が亡くなったあと「撮りためた映像から映画を作らないか」とお話をいただいたのですが、本来なら先生がお元気な間に完成させて「なんでこんなとこ撮ってたのッ」と怒られるはずでした。でも急に具合が悪くなられて、間に合わなかった。映画は『瀬戸内寂聴 99年生きて思うこと』という作品となり、2022年5月に公開され、一段落してモチベーションを失ってぼーっとしていたところ、今回の映画の益田プロデューサーから「グリーフケアをやらないか」と声がかかりました。
グリーフケアなんて聞いたこともない言葉でしたが、このお誘いは断りたくなかったのでどんどん巻き込まれていき、さまざまな方にお会いしたり、本を読んだりしているうちに「これはすごく大事なテーマだな」と気づきました。やってみようと決心したのが2022年7月。当初ケーブルTVの番組として企画されたので予算規模が小さく、インタビューベースにしようとリサーチを始めて、2022年8月には最初のロケに出ています。
――リサーチをすすめるにつれて、だんだん「ぜひやりたい」という気持ちになっていったのでしょうか?
とんでもない、その逆で、知れば知るほど断りたくなりました。だって、間違いなく最初から最後までつらい体験を語ってもらう作品です。ぼくはどういう顔でそのつらい話を聞いていけばいいのか。相手の方は、きっと話してるうちに思いがよみがえり、泣いてしまうこともあるでしょう。そんなときぼくはその人の前にどう座っているのか、想像もつきませんでした。ドキュメンタリーではそういうとき「あなたの声を多くの人に伝えたいんです」と言ったりもしますが、そういう常套句で済ませてはならないぞと感じていたのです。
ぼくは日ごろから、どう撮るかではなく、「なぜ撮るか」が大事だと思っています。そして、「なぜこの題材を選ぶのか」を突き詰めないと、「なぜ撮るのか」答えは見つかりません。できあがったあとから考えると、つらい思いを抱えて答えてくれたそれぞれの人たちの、さまざまな言葉の分だけ、いろいろな人に届く作品になったと感じます。作中、上智大学グリーフケア研究所元所長の島薗進先生が「人間は生きている限り喪失の連続であり、その分だけグリーフ、悲嘆がある」と語ります。でも、悲嘆にどう対応するかは個人によって違います。ですので、この題材をさまざまな人が登場するインタビュー形式で撮った意味はそこにあったと感じます。

作中より、上智大学グリーフケア研究所元所長の島薗進先生。
――お話を聞き続けるうちに、さまざまな「グリーフ」に対するベターな対峙の道が見えていったのでしょうか?
いいえ、結局、何度取材を重ねても、最後までまったくわかりませんでした。ただ、今回は取材を進めるにつれて「癒し」という言葉を安易に使うのはやめようという気持ちが固まりました。癒したり癒されたりって、そんなにライトじゃないだろうという思いが生まれてきたんです。悲しみは人によって全然違うから、「あなたを癒してあげようというような気持ちで他人に接すると悪い方向に行くだろう」と感じられたのです。
みなさんのお気持ちを聞いていくと、やはり誰かの悲嘆に向き合うことはそう簡単ではありません。かなりの訓練が必要です。とにかく一緒にいてほしい、寄り添ってほしい、言葉なんかかけてくれなくていい、ただ自分の悲しみを聞いてほしいという人たちにちょうどよく向きあうのは非常に難しいことです。

作中より、飛騨高山がんサークルOwls代表の三井祐子さん。
そんな中、自分も悲嘆を抱える人が一生懸命訓練して、誰か別の人の役に立とうとする姿に触れ、魂の進化と呼ぶべきものがこの世にあるならこれだなと感じました。大阪教育大学附属池田小学校事件で娘さんを失った本郷さん、がんサバイバーかつ自死遺族の三井さんらは、喪失の渦中ですでに「この体験が他の誰かの役に立つかもしれない」と考え始めています。そんなことおじさんには思いつきません、ぼくならひたすら打ちひしがれていると思います。
悲嘆の本質とは「愛」である…一瞬理解できないこの概念がやがて腑に落ちていく

作中より、グリーフパートナー歩み代表の本郷由美子さん。
――ドキュメンタリー関係者なら遺族コメントなんて取り慣れているだろうと思われがちですが、そんなことはないんですね。
ないです。事件取材の経験もあまりないですし。ドキュメンタリーで相手が聞いてほしくないことを敢えて聞いて深層心理に切り込むことはありますが、この作品はそんなレベルではない、傷口を深くえぐるようなことばかりを聞くんです。質問事項を事前にお渡ししてはいますが、それでも「これを聞いていいのだろうか」「どんな顔をして聞いたらいいのだろうか」と迷います。最終的には自分の居住まいを常に正して向き合わざるを得なかった。
相手を見つめる側であるはずの自分が、逆に人としての本質の部分まで見透かされているような感覚が常にありました。どれだけ真剣にいまこの瞬間向き合っているのかを問われている感覚です。質問するこの声のトーンひとつも迷いながらです。いまこの人と真剣に向き合わないとこの質問そのものが成立しない、ただ質問を聞きましたというだけでは絶対にダメだという緊迫感に追いかけられていました。
――そんな数々の取材は当時に、悲しみの本質がじつは「愛」だという話に納得していく過程でもあったそうですね。
はい、事前にいろいろ学習する中で「悲しみの根底、本質には愛がある」という言葉に触れ、どういうことなんだろうとずっとひっかかっていました。愛というと、日本語では男女の恋愛を想起しますが、実際には親子の愛、友人の愛、ペットへの愛、いろいろな愛の形があります。ゆえに、何であれ失うことは悲しい。今回の大きなテーマは喪失の背景に等量ある愛です。そして、悲しみの本質に愛があったと気づくことから、みなさんそれぞれに立ち直るきっかけが見つかっていくのです。
明治期、海外から入ってきた言葉を日本語に訳すとき、旧約聖書に書かれたLOVEが何であるか日本人にはよくわからず、「力」と訳した人もいたそうです。愛という概念は、それ以前には流通していなかったのですね。ですが男女間だけでなく、親子の間に流れるこの気持ちも愛だと説明がつき、大切なものを亡くすという悲劇的な体験の中で愛の正体に気づく。それが人の成長につながるのだということは今回はじめて理解しましたし、ぼくにとっては非常に大きな体験でした。
前編では映画の取材に至る経緯を伺いました。つづく後編では中村監督のグリーフと、瀬戸内寂聴先生に「言えなかったこと」を独白します。
つづき>>>「プリプリ怒る瀬戸内寂聴先生と一緒に酒を飲みたかった」グリーフケアを撮る監督が語る自身の「喪失と悲嘆」との向き合い方
スポンサーリンク
【注目の記事】
- 「若作りが痛いオバサン顏」の原因は「黄みがかったブラウン眉」のせい?40・50代が買ってはいけないアイブロウアイテム
- 思春期ど真ん中の高2男子が変わった!ゲームと動画で夜更かし三昧→翌朝起きられない…のダラダラ生活が、スマートウオッチつけたら別人級に
- 40代以降の「肌の変化」どう向き合う? 赤のジェリーでおなじみ「アスタリフト」たった7日試しただけで「わかったこと」とは!
- 【強烈寒波の防寒はコレ!】48歳「冷えに悩む」PTA中受ママが「温活にハマった」結果、家でも外でも「つけっぱなし」!暖房代も節約できるあったかグッズとは?
- 【強烈寒波の防寒はコレ!】48歳「冷えに悩む」PTA中受ママが「温活にハマった」結果、家でも外でも「つけっぱなし」!暖房代も節約できるあったかグッズとは?
スポンサーリンク