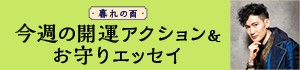「普通」って何? ADHD本人、家族の葛藤と苦悩とは? 【発達障害を映画化。北 宗羽介監督と考える】
発達障害だと認めたくない家族
北さんは、この映画を制作する前から発達障害と思われる人と関わってきたそうです。目をかけていた俳優さんが発達障害ではないかと思った時のこと。
「その人は子どもではなく成人した俳優さんだったのですが、約束した時間を忘れるし遅刻も多い。注意散漫で人の話を聞いていないのではないかとか思うこともしばしばありました。プライベートならまだしも、仕事に関することなので、しょっちゅう関係者に迷惑をかけてしまう。私は、その子のマネージメントやプロデュースに力を入れていたので、なんとかしたいと思い、今まで診察やカウンセリングを受けたことがあるのか、ないのであれば診てもらってはどうかという話をしました。」
ところが、何日か経って、その人の親御さんから電話がかかってきたそうです。
「そんなこと言わないでくれと言われました。その子はADHDに加えてASDも入っていたと思いますが、多分、家族はあまり見ないようにしてきたのだと思います。親は分かっていても見たくないではと感じました。だから、病院に行ったり、専門の医師に診てもらったりすることをしなかったのではないかと想像しました。子どもの頃はそれで通せたのかもしれません。しかし、その人が社会に出ていろんな人と関わるようになった時、遅刻してしまうとか物忘れしてしまうという症状が表に出てきて問題になったのです。」
遅刻や物忘れ、誰にでもあることのようですが、そんな生やさしいものではなかったと北さんは振り返ります。
「その人は、異様とも言えるほど頻回に問題を起こしました。遅刻が多く、言ったことを覚えていないことも多々ありました。こういうふうに行動してねとか、これをやっておいてねと伝えても、結構簡単なこともできませんでした。映画でも、絃(いと)の母親が、絃に注意するシーンがあるのですが、発達障害は気をつけて治るような問題ではないと実感しました。」
病院には連れて行きたくない

母親に「気をつければ普通の人になれるわ」と言われてしまう絃。
北さんは、発達障害の疑いがあるのに、病院に連れて行かない親に疑問を持ちました。
「先日、精神科の先生と対談したのですが、『発達障害』という名前がついてしまっているので、子どもを病院に連れて来ない親御さんがたくさんいるそうです。そこで、その先生が、『子どもの頃におかしいと思ったら診ます』という、病院とは違うシステムを作ったのですが、あまり来なかったそうです。親御さんは、幼い子どもに『障害』という名前の病名がつくことが耐えられないでしょうし、いつか治るのではないかという淡い期待も抱くのでしょう。子どもが小さければ小さいほどそういう親御さんが多いらしく、施設に来ない。『発達障害』という名前がつくことで、周りの人に『この子は障害を持っている子だよ』と見られてしまう。だから病院には行かないという人も多いようです。」
我が子を精神障害者だと思われたくないという気持ちと不安な気持ちがせめぎ合うのですが、そこには何が必要なのでしょうか。
「先生は、いきなり医療にかかるというと身構えてしまうので、カウンセリングを受けられる相談所みたいなところがあったらハードルが下がっていいのではないかとおっしゃっていました。自治体が主導して、なるべくハードルを下げる仕組みや機関を作ることが望ましいと思います。」
グレーゾーンの葛藤

友達が言ったことを忘れてしまうことも。
映画では、朱里と絃の両親が目の前で起こっていることを受容しきれず、本人に辛く当たってしまうシーンがあります。
「朱里の方は、それほど重度な発達障害ではないので、障害者手帳も貰えません。だから、発達障害と診断されているにも関わらず、家族は、『全然普通なんだから、甘えていないでちゃんとしなさい』と言ってしまいます。絃の方は、親が発達障害そのものを否定するというか、発達障害と診断されているのに、『あなたは発達障害ではない、ちゃんとしなさい』と否定してしまう。要は、どちらの両親もあまり現実を直視したくないのです。」
確かに、彼女たちのようなグレーゾーンの人は、家族も「発達障害ではないかもしれない」と期待してしまうかもしれませんし、「ちゃんとしなさい」といういらだちを感じることもあるでしょう。
「重度だったら分かりやすいかと思います。多動で落ち着きがないとか、物忘れが激しすぎるとか、たぶん対処の仕方があると思います。しかし、グレーゾーンの人たち、すごく軽い症状の人たち、いわゆる普通の人と病気の人の間にいる人たちは、どちらにも区分けできてしまいます。世の中にはそういう人が10%くらいいると見られていて、その人たちが社会に馴染めなくて苦しんでいます。だからと言って、はっきり精神障害者と認定されるとあまりいい仕事に就けないという雇用の問題もあるので、あえて診断を受けない、障害者手帳を貰わないという人も少なくないでしょう。」
朱里と絃は発達障害と診断されていますが、学校では普通級に入っています。二人とも普通級にも馴染めず、かといって重度というわけでもありません。それゆえに居場所がありません。
「学生の場合、重度であれば特別支援学級で対処できますが、軽度の人は通常の学級に入れられます。そこでは、学校の先生やクラスメートの理解を得られなかったり、誤解されたりすることがあります。『お前なんだよ、困った奴だな』ということになり、排除されたり特別な目で見られたりしてしまいます。そういう問題がグレーゾーンの人には多いのではないかと思います。」
朱里の通う学校は偏差値が低め、絃が通う学校は進学校。それぞれ周囲の反応も違います。
「たぶん、朱里の学校の方が陽性というか、言葉は悪いですがあまり頭の良くない学校ですが、多様性があります。でも、そういうところに来る子たちは強く当たってしまう傾向にあります。ネットの世界でも、『本当にお前、障害持っているのか』とか『障害者だろ』とか直接的で強い言葉を軽い気持ちで言ってしまう。絃の学校は頭のいい学校ですが、皮肉を言うとかネチネチした感じのイジメになるのかなと思います。発達障害に限らず変な子がいると、『お前、ガイジ(障害児)だろ』とか汚い言葉を平気で言う。言っている本人に悪気はなく、軽い気持ちで口にするのですが、言われた側はグサっと胸に刺さります。」
「普通」と「障害」の境界で苦しむ発達障害の人たちと現実を受け入れたくない家族。解決の糸口はあるのでしょうか。後編では、ニューロダイバーシティや明るい発達障害の人にも話を広げます。
【岡田俊先生のここがポイント!】
発達障害の症状は、日常生活の中に現れますが、その症状は捉えがたいものです。ADHDの診断基準をみても、どのエピソードも、すべての人が経験したことがあるエピソードです。それが、同じ発達水準の人と比べたときに顕著であり、日常生活に支障を来すレベルであるのかによって診断がつくのです。人は皆違います。ADHDは一つではないかという質問は、ある意味では正しく、ある意味では間違っています。ADHDも個性の延長線上にあり、同時に個性という言葉では片付けられない水準であるとき、診断名が付くのです。ADHDは、目に見えない障害の典型例といえましょう。
診断名が受け入れにくいのは、家族だけではなく、本人も同じです。うつ病や不安症など、さまざまな病院で診断されても納得せず、ようやくADHDという診断にたどり着くことがあります。本人は、自分の生きづらさを説明する何かをもとめてきて、ようやくそれを手にしたわけです。
しかし、その診断を受け止め、その診断とともにどのように生きていけば良いのかについては、まだ答えを見い出せていないのです。
周囲からの無理解な言動について、「私はADHDだから」と返答をするかもしれません。これが客観的な事実であったとしても、周囲からは診断のせいにして、改善する気持ちがない、診断に甘えていると言われてしまいます。家族は、その子がADHDと診断されるということを知的には理解していても、その現実をまだ受け止め切れてはいません。診断を受け入れることが、子どもの将来をあきらめることだと思ってしまうこともあります。すると、思わず心にもない言葉が出てしまい、子ども、家族ともに悲しい思いをしてしまいます。本人も、家族も、決して現状に甘んじようとしているわけではありません。なのに、互いに掛け違ってしまう、ということが起こるのです。
障害が重ければ重いほど、もちろん大変さも大きいのです。しかし、軽ければ軽いことに伴う悩みもあります。本人も周囲もその大変さが分かりにくい、だからこそ掛け違いが起こりやすくなります。
発達障害についての知識は非常に広まってきました。そして、発達障害についての理解の必要性も広く認識されています。ただ、しばしば聞かれるのは、「理解する必要性は分かっているが、どうして発達障害でない人だけが我慢しなければならないのか」というコメントです。このようなお話をお聞きすると寂しい気持ちになる一方、このようなコメントをされる方は、真摯に向き合おうとされている、思うようにことが運ばない時に感じる率直なコメントだとも思います。つまり、発達障害を理解しようと思うのですが、「具体的にどうすれば良いのか」ということが分からない。
また、周囲の方々も皆かつかつのところで頑張っているということです。この調整には、ご本人の特性を理解した上で調整を図るなどの専門的な知識が必要となることがあります。学校は、通級指導教諭や養護教諭、特別支援学級担任やスクールカウンセラーなどもいますし、職場でも産業医やカウンセラーなどが調整に当たることもあります。医療や福祉も支援に当たっています。本人、家族、そして周囲の人にとっても、一人の力だけで解決することは難しいこと。相談の輪を適切に広げていくことが大切です。
【前編】では、ADHDゆえに生きづらさを抱えているふたりの高校生を描いた映画『ノルマル 17 歳。 ― わたしたちは ADHD ―』と、そこに描かれた当事者と家族の葛藤についてお伝えしました。
▶つづきの【後編】では、大人の発達障害について、社会との共存のしかたについてお伝えします。__▶▶▶▶▶
【国立精神・神経医療研究センター・岡田俊先生】

岡田 俊 先生
国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所知的・発達障害研究部部長/奈良県立医科大学精神医学講座教授
1997年京都大学医学部卒業。同附属病院精神科神経科に入局。関連病院での勤務を経て、同大学院博士課程(精神医学)に入学。京都大学医学部附属病院精神科神経科(児童外来担当)、デイケア診療部、京都大学大学院医学研究科精神医学講座講師を経て、2011年より名古屋大学医学部附属病院親と子どもの心療科講師、2013年より准教授、2020年より国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所知的・発達障害研究部部長、2023年より奈良県立医科大学精神医学講座教授。
映画 『ノルマル 17 歳。 ― わたしたちは ADHD ―』

監督の北宗羽介氏。映画プロデューサー/映画監督/脚本家。

神田凛さん。「ノルマル17歳ーわたしたちはADHDー」で脚本家としてデビュー。高校生の時、知り合いが発達障害だったので関心を持ったという。
東京・アップリンク吉祥寺にて絶賛上映中(全国順次)出演:鈴木心緒、西川茉莉、眞鍋かをり、福澤 朗、村野武範 、小池首領、今西ひろこ、花岡昊芽 ほか
監督:北 宗羽介 脚本:神田 凜、北 宗羽介、音楽:西田衣見 撮影:ヤギシタヨシカツ(J.S.C.)、エグゼクティブ・プロデューサー:下原寛史(トラストクリエイティブプロモーション)、プロデューサー:北 宗羽介、近貞 博、斎藤直人、製作:八艶、トラストフィールディング 配給:アルケミーブラザース、八艶
後援:一般社団法人日本発達障害ネットワーク(JDDnet)、NPO法人えじそんくらぶ ほか
文化庁「ARTS for the future!2」補助対象事業
©2023 八艶・トラストフィールディング /80 分/カラー/5.1ch
https://normal17.com
【編集部より】
あなたや周囲に発達障害とともに暮らす方はいませんか? 生きづらさ、困っていることなど、お話を聞かせてください。 こちらから
1 2
スポンサーリンク