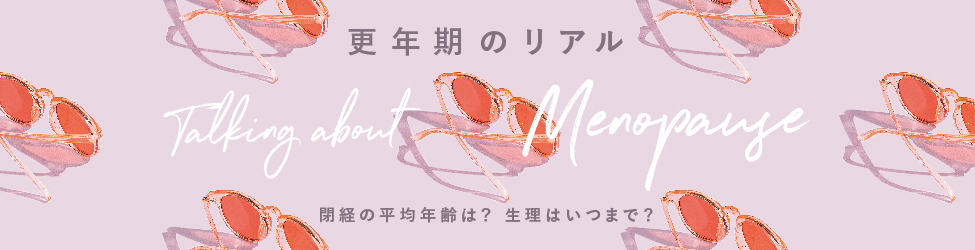がんの末期は「絶望のドラマ」なのか。すい臓がんで体重が40㎏台になった父と過ごした最期。それでも「家族の日常は消えない」
がんになっても「家族の日常は消えない」と気付いた日
陽射しが差し込むリビングで、2人はお茶を飲みながら他愛もない会話をしている。話すのは母が中心で、父はテレビに目を向けながら、適当に相槌を打つ。それでも母は気にすることなく、楽しそう。
これまでずっと目にしてきた光景を、久しぶりに目の当たりにし、私は急に満たされた気持ちになりました。そして、あることに気付くのです。父が「抗がん剤治療はせず、住み慣れた家で、このまま穏やかな時間を過ごす」という道を選んだのは、この「日常」を家族で感じ続けるため。
そして、それは誰よりも私が求めていたことだった、と。
父ががんにり患して、すぐに私は絶望的な気持ちになりました。父は「がんになった人」、母と私は「看護(介護)する人」として、これからは、その関係性でのみ会話を交わすことになるのだろう。「日常」は、次第に消えてゆくと思っていたのです。
しかし、今あるのは、かつての見慣れた景色で、たとえ父が病気で痩せてしまったとしても、目の前にいる2人に何も変わった様子はない。
「がんになっても、ちゃんと『日常』はあるんだよ」私はそのとき、父からそう教えられたような気がしました。
▶父と一緒にした「終活」が、親子の思い出を増やしてくれた
この記事は
ライター
小林真由美
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク