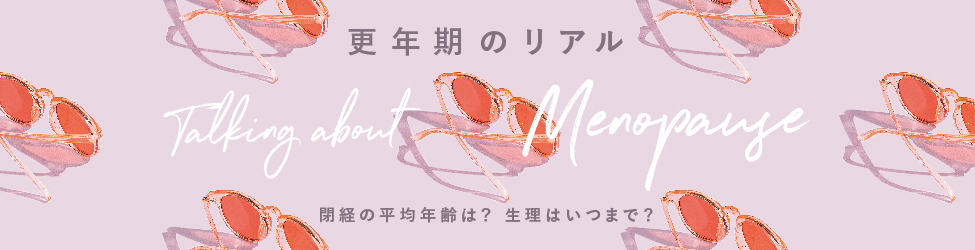平安時代の「働く女性」たちの意外すぎる「働く動機」とは?「確かに、それなら家が貴族でも働くわ」
*TOP画像/ききょう(ファーストサマーウイカ) 大河ドラマ「光る君へ」14回(4月7日放送)より(C)NHK
『光る君へ』ファンのみなさんが本作をより深く理解し、楽しめるように、40代50代働く女性の目線で毎話、作品の背景を深掘り解説していきます。今回は清少納言の人物像を見ていきましょう。
前編『平安時代にもありました!「港区結婚ゴール女子」VS「丸の内バリキャリ」の火花!【NHK大河『光る君へ』#14】』に続く後編です。
知的でクールな清少納言は「定子さま推し」だった!?
清少納言は歌人・清原元輔の末娘として生まれました。清少納言はニックネームのようなもの。本名は清原何子という説もありますが不確かです。
清少納言は結婚や出産、離婚、両親の死を30歳になる前に経験しています。人生の悲しみを若くして味わった彼女。28歳の頃に宮中に入り、藤原道隆の娘(道長の姪)・定子の女房になります。
清少納言は定子よりも10歳ほど年上。清少納言は定子の美しさや優しさ、聡明さに惹かれ、彼女を尊敬し、好意を過剰なほど抱いたといわれています。

定子(高畑充希) 大河ドラマ「光る君へ」13回(3月31日放送)より(C)NHK
同性に対してときめきの対象、あるいは“推し”として認識することもありますが、清少納言の定子に対する想いはそれに近いものでした。「定子が大勢の女房の中で自分に目を合わせて話してくれてうれしい」「定子の指先がうつくしい」などと『枕草子』に書き綴っています。
清少納言はかわいいものが好きで、年下の人に対してあたたかいまなざしを注ぐタイプだったのかもしれません。『枕草子』には「少女が薄紫色の着物の上に白の上着を着た姿」や「いちごを食べる幼い子」があてなるもの(上品なもの・優美なもの)として綴られています。
宮中での暮らしも性に合っていた清少納言ですが、道長側に転がったのではないかと女房から疑惑をかけられたこともあります。これをきっかけに里に下がり、定子から戻ってくるよう告げられても応えられない日々が続きました。(知的なコミュ力高め女子でも根も葉もないウワサには弱いんですね)
最終的に、清少納言は定子のもとに戻り、彼女が厳しい状況にあるときも女房として傍で支え続けたと伝わっています。
当時のイケメン男子とも仲良くしていた清少納言。女子力が高いイケてる女性
紫式部は宮中での暮らしに馴染めず、実家に一時的に戻りました。邪気を祓うための薬玉を里居期間に受け取るも、「菖蒲(しょうぶ)の根が水底に隠れて濡れているよう、私は家にこもって涙に濡れている」といった歌を返すにすぎませんでした。
一方、清少納言はコミュ力が高く、明朗快活とした性格であったため、宮中での暮らしに比較的はやく適応できたようです。賢く、機転が利くため、同性からも異性からも人気がありました。
定子サロンには約30名の女房がすでに所属していましたが、清少納言は定子から他の女房以上に寵遇を受け、サロンにおける中心的人物となります。
また、現代において清少納言はイケメン好きとして知られています。『枕草子』には「説教の講師は顔がよくなくては」と書かれています。(私たちも担任の先生や講師がイケメンだったらうれしいですよね!)
清少納言は和歌が得意ではなかったものの、漢文に長けていました。彼女は漢文の素養を発揮して男性たちと宮中で交遊していたそう。定子サロンには和歌が得意な男性ばかりではなかったため、清少納言のように漢籍に長けた女性は魅力的だったようです。彼女は女房たちから美男子と好評の藤原斉信(※)とも親しくしていました。
清少納言がオシャレ好きな女性であったことは「髪を洗って、お化粧して、よい香りの着物を着ると心ときめきする」という『枕草子』の記述にもうかがえます。着飾って出かけた日に限って、だれにも会わなかった日はがっかりしたとも本書に綴っています。
※太政大臣・藤原為光の次男。和歌や漢詩、朗詠、管絃に長けており、当代随一の文化人として知られていた。
清少納言が勧めた
当時、宮中といえば、中下級貴族の姫たちにとって憧れの職場でした。今でいうと、霞が関で働く国家公務員や宮内庁職員、あるいは超大手企業の重役秘書といったイメージでしょうか。
宮中で働けば、中下級貴族の暮らしでは縁がない調度品や文化にふれられるだけでなく、天皇や后、その子どもたちの生活を垣間見ることもできます。
清少納言は女房の仕事に当初から肯定的であり、宮中に入ってからも自分がおかれている状況に満足していたことは、『枕草子』における以下の記述にもうかがえます。
おひさきなく、まめやかに、えせざいはひなど見てゐたらむ人は、いぶせくあなづらはしく思ひやられて、なほさりぬべからむ人の娘などは、さしまじらはせ、世の有様も見せ習はさまほしう、内侍のすけなどにてしばしもあらせばやとこそ覚ゆれ。
将来に対してたいした望みをもつこともなく、ただただ真面目に生き、ニセモノの幸福にしがみついていたいと考えるような人たちって鬱陶しく、軽蔑したくなる。それ相応の家柄の娘であっても宮中に出仕し、世の中を見てほしいし、典侍の役職にでも少し就いてみたらどうなの。
清少納言『枕草子』
当時の社会では女性に対して“御簾(みす)の奥に隠れているくらいがちょうどよい”、“女性は人に顔をさらして働くものではない”という見方もありましたが、ここではこうした女性像が否定されています。
それどころか、彼女はきちんとした家柄の娘であっても宮仕えをし、世の中を見てみること、そして典侍(※)を経験すべきであると説いているのです。
一夫多妻制が認められていた当時、女性が夫に複数の妻や妾がいることを快く受け入れていたわけではありません。夫が他の女の屋敷に通う姿を見て、複雑な気持ちになる女性も当然いました。男性に振りまわされる女性というのはいつの時代もいるのです。
また、平安時代の女性の幸せは現代人の価値観では語れないものの、部屋にこもってばかりいては人生を謳歌しているとはいえないでしょう。屋敷にひきこもっているよりも、宮中でさまざまなものにふれ、多くの人と関わる暮らしに充実感を抱く人も多いはずです。
私たちだって職場の人間関係をわずらわしく思ったり、仕事が大変だと感じたりすることもありますよね。とはいえ、同僚の顔を見ると笑顔になったり、憧れの上司にときめいたり、仕事をしていなければふれられないものがあるのも事実。「宮仕えなんてイヤ~!」と言っていた紫式部も同僚と雑談など楽しんでいたようですよ。
※典侍とは女官によってのみ構成される内侍司(ないしのつかさ)における次官のポジション。
参考資料
・清少納言(佐々木和歌子訳)『枕草子』光文社 2024年
・倉本一宏(監修)『大河ドラマ 光る君へ 紫式部とその時代』宝島社 2023年
・木村朗子『紫式部と男たち』文春新書 2023年
スポンサーリンク
【注目の記事】
- 女性の多くが経験する「尿トラブル」、家庭で効率よく向き合うケアアイテムが新登場! 骨盤底筋専用EMS「SIXPAD ペリネフィット」
- 細リブニットで作る大人の甘辛モノトーンと体型カバー法【40代の毎日コーデ】
- 必要なのは「努力」ではなく「適切なギア」と「正しい数値化」でした! ゆらぎ時期の54歳がガーミンのスマートウォッチで「睡眠・生活の質」を爆上げした話
- 「勝手にトイレ入るな!」と連れ子をいじめる偏愛夫(38歳・公務員)。再婚→また離婚…夫の「仕事上の弱み」を把握すれば、実子の親権も養育費も得られる!?
- わずか小さじ1杯!女性ホルモンの“悪い代謝”を”よい代謝”へ導き、数日で細胞が1カ月で肌が若返るオイルとは?美人女医の実践方法も取材【消化器内科医監修】
スポンサーリンク