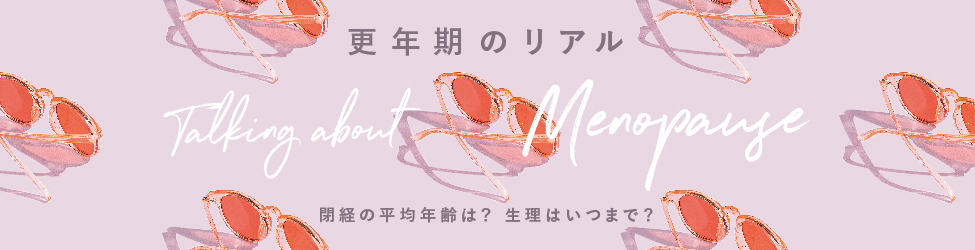なぜ宇治の緑茶は「旨い」のか?「テロワール思考」を知れば、私たちの喜びは8割がた説明がつく
複数の学問領域が交差する部分、いわゆる「学際」は、学問同士が接触しあい新しい解釈を生み出そうとしているとてもエキサイティングな領域。
都市建築史から祝祭、食に発想を広げつつ、地理学・建築学・歴史学・経済史学との学際研究として「テロワール」研究にいきついたのが京都工芸繊維大学デザイン・建築学系准教授の
と言われても「????」かもしれません。
ちょっと視点を変えましょう。私たちが「新潟の日本酒」や「宇治の緑茶」、「有明の海苔」などが大好きな理由って何だと思いますか? この「テロワール」の観点から日本を捉えると、それらは「当然、誰だって大好きになる!!」のです。
四季の恵み豊かな日本という国だからこそ楽しめる「テロワール」、当たり前のように周囲にありすぎるから、私たちはちょっと無自覚かもしれません。鎌倉と京都、日本の2大歴史都市に馴染み深い赤松先生ならではの視点で、おいしくて楽しい最新の学際研究エッセイをお届けします。
(トップ画像・宇治茶産地和束町茶畑景観の調査を行う筆者)
はじめに:どこに足をつければいいのか? 振り返ってほしい「テロワール思考」
アスファルトだらけの都市の暑さは、身にこたえる。
野菜高騰で家庭菜園でも借りようと思うが、気づけば周りの「土」が本当に減った。
土は再生できない資源であるにもかかわらず、家を建て、ダムや都市をつくるなかで
わたしたちは、あまりにあたりまえに「土」や「大地」、そして「地域」を消費してきてしまった。
今、土地や地域に根ざしたものづくりや暮らしに惹きつけられるのは
あえて持続再生やSDGsと叫ばなくても、わたしたちなりの調整作用なのかもしれない。
しかし、どこに足をつけ、地域に根差して、未来を考えたら良いのか。
そこで一つの思考法としておすすめしたいのがテロワール思考だ。
テロワールとは何か:自然と人間の合同作品としての地域
ワインが好きな方は聞いたことがあると思うが、
「テロワール」とは、「ワインの味・香りの個性をつくる自然と人間の合作としての土地・地域」のこと。
古くは狭義にワインの性格をつくる「土壌」だけを指した。
たとえばブルゴーニュワイン。
中世に修道士たちが開墾した畑には、小さな区画ごとに名前がつけられた。
なぜなら畑ごとにブドウの味や香りが違ったから。
ワインに個性を与える土質、日当たり、水ハケに特徴を持つ土地のこと、それがテロワールの原型である。
ブルゴーニュではこの畑区画のことをクリマと呼び、
歴史的・文化的な価値が評価され2015年に世界遺産登録されている。

ブルゴーニュの畑。区画が分かれているのが遠くからも見えます。
しかし、ブルゴーニュのような土地は稀だ。
他の多くのワイン産地では複数の畑・ブドウをアッサンブラージュ(調合)してワインができあがる。
シャンパーニュもボルドーも、人間の経験知や消費文化によってその土地の味は作り上げられてきた。
たとえば、ボルドーにはたくさんの有名シャトーがある。
マルゴーやラフィットといった5大シャトーをはじめ、ほとんどのボルドーワインは一つの畑区画の葡萄でできているとは限らない。むしろ異なる畑で育てられたメルロー、カベルネ・ソーヴィニヨンといった複数の葡萄が、人の手によって調合されたものだ。
それにも関わらず、ワインマスターたちがテイスティングをすれば、どこのシャトーの、何年のヴィンテージかがわかるのは、自然環境以上に人間が作り出した固有の味の特徴があるからだ。
つまり、自然が用意したデフォルトの環境に、人間が手をかけ、知恵を重ねて作りあげてきた土地、それがテロワールなのだ。
近年「テロワール」は「土壌」を指すよりも、そこに関わってきた人間の営みを重要視する捉え方になってきている。
まさに人間が自然環境の中で生き、暮らしてきたという営みと痕跡こそがテロワールを作り出してきた。広義にいえば歴史的・文化的総体としての「地域」そのものがテロワールなのだ。
テロワールは歴史と経験からつくられた価値
この「テロワール」というメガネをかけてみると、
「地域」とは、長い歴史の中で、自然と人間が何かを作るという共同作業を通じて作ってきた合同作品であることが実感できよう。
右の図を見てもらえるとわかるように、自然が与えてくれる地質、土地、気候といった条件と、それを加工、流通、消費、評価を行うことで特徴を付加させてきたテロワールの構成がイメージできるだろう。

調査先のサン=テミリオンのシャトー・クーテットの貯蔵空間。

明治時代の茶工場に残る手揉加工のための焙炉。
たとえば、地域によってワインの樽の大きさは異なる。
その違いは醸造空間や輸送貨物のサイズに影響を与え、固有の地域文化を作ってきた。
また宮廷向けなのか、大衆向けなのかと言った嗜好のちがいや、
市場の評価やニーズのフィードバックがテロワールを進化させてきた。
テロワールは一朝一夕ではできないものだ。
深い歴史性とそこでしかできない固有の経験、それがあってできあがる。
異なる個性と価値を持つ、唯一無二の存在なのである。

古代ローマ人が掘った採石場が現在の醸造空間として生かされている
少し古い言い方で言えば、テロワールの価値はナンバーワンじゃなくオンリーワンなのである。
今や、世界が多様化して自由に繋がれる時代になったからこそ、その土地、地域のテロワールを理解し価値を尊重することは、持続可能な社会を築く上で重要となる。
たとえば、とある地域に、歴史を無視した新しいアイデアや産品を持ち込んでみたとしよう。
地域の歴史を知らずに持ち込まれたそのモノは、やがて自然環境に淘汰されるか、地域社会から排他される。
なぜなら、歴史は進化の例証。歴史あるものには生き残ってきた理由があるわけで、歴史はすべてのヒントになる。
何を大事にするべきかは、土地で培われてきた自然と人間の対話に学び、
積み上げられてきた価値を読み取ることによって、自ずと見えてくる。
未来を描くために自然と人間の対話の歴史を知ること、テロワール思考はそこに始まる。
都市なくしてテロワールなし:都市と農村の二項対立から進化し、両者の循環系に成り立つ地域文化を捉えるテロワール
テロワールは、フランスワインで醸成されてきた概念だ。
しかし、その枠組みはワインにとどまらない。
近世フランスではチーズやソーセージといった地域固有の高付加価値の希少産品は、テロワール産品として認識されてきたし、アジアをみるとお茶も実はテロワール産品であることに気づく。
日本茶も八女、宇治、静岡など土地、加工製法にもとづく多様な種類があり、それぞれの地域の歴史的性格を反映しているし、中国茶となればさらに熟成によるヴィンテージも発生し、まさにワインと同様、自然と人間の合同作品ということができる。

宇治茶の覆下栽培。茶葉の味を柔らかく保つために本よしずで陽を遮る工夫は昔からのもの。
さらに、ワインとお茶に共通するのは、都市文化によって評価されることで味の違いが確立されてきたという歴史である。
ワインの格付けの初出は1855年のパリ万博と言われるが、同時期、宇治茶でも番付表が作られ、味の違いと個性が認識されていたことがわかっている。
テロワールは生産者の丹念な営みがあってこそ作られる土地だが、食や嗜好文化を謳歌し消費する都市文化があってこそ、土地の価値が見出され、認められてきたわけだ。
テロワールという目線でワインやお茶を見つめると、
農村と都市を二項対立させるのではなく、生産文化と消費文化が循環しながら作ってきたことに気付かされる。
そこに気付くには、どちらが川上であるとか、搾取されるといった発想を乗り越え、互いのシゴトへの尊重と感謝の眼差しが必要だ。
都市なくしてテロワールなし、地域の歴史なくして美食なし、そう考えて良いだろう。
つまり土地に根ざすということは、それを包み込んできた集落、都市、文化圏との交流、交換という大きな視野を持つということにほかならない。
テロワールから見えてくる欲望の轍「人新世」への反省
このように、テロワールは土地を理解し価値を見出す上で魅力的な見方である。
しかしその一方で、テロワールは人間の負の轍に猛省を促すものでもある。
その一つが「人新世」とのシンクロニシティだ。
「人新世(アントロポセーンAnthropocene)」とは、人類が作りだしてしまった新たな地質年代のことだ。石炭や石油を大量に消費し、大量排出される二酸化炭素が、地球環境を変質させてきた250年頃以来の地層時代として、ノーベル賞受賞の大気化学者パウル・クルッツェンが2002年に指摘したことに始まる。
人新世の地球は、わたしたちの子孫の身体を変質させうる大量の合成化合物に満ちていて、温暖化、異常気象、大災害をはらんでいる。
実は人新世の始まりとワイン産業の拡大は見事にリンクする。
人新世の始まりは石炭の燃焼による大気の「炭素化」が始まる1750年頃からとされる(パウル・クルッツェン、2002)。
ワイン生産、流通、消費の超拡大もその頃。フランスでは1789年の革命以降、多くの葡萄畑がブルジョワジーの手に渡り、多くの人々がワインを愛飲するようになっていたし、シャンパーニュ地方ではロシア、アメリカに至る地球規模の販路が拡大されていった。あらゆる畑で土地改良が進展し、戦争と兵器開発と共に多くの農業技術が革新的発展を遂げたことは藤原辰志が指摘する通りだ。
ワインには質と量を求める人間の欲望が露呈する。その欲望の足元に人新世の地質が生見出されていったことを見過ごすことはできない。飽食の時代、過去の過ちに気づき、次は間違えない価値観を持つために、テロワールは一つの注意喚起を促してもいる。
地に足をつけた統合的価値:個性と多様性を受け止めるために
まとめよう。
テロワールという価値観でモノゴトを捉えると、ワインや茶といった土地に根ざした産品の魅力がひときわ深く感じられる。そこには歴史と経験がつくった個性があるからだ。そう考えるとテロワールは未来に向かう道標となる。
どこに進んでいったら良いのか。
その答えは、テロワールをつくった自然と人間の対話の歴史に問いかけること、にある。
そこにこそ、そこにしかない「本質」を保ちながら、未来へと進化するヒントが隠れている。
極端にいえば、人間もテロワールだ。
中世フランスでは人間の欠点を示すときに「テロワール」を用いたというから、あながち間違ってもいない。たしかにわたしという人間も、与えられた生育環境の中で、さまざまな経験を経てできた歴史的総体というテロワールだ。土地のテロワールを尊重するように、一人一人の人間のテロワールの個性と多様性を受け止められれば差別も戦争もなくなるだろう。
テロワールの価値とは自然、人間、過去、現在、未来が収斂した統合的なものだ。
人間のテロワールがあると考えるなら、
地域に根ざした価値創造も、普段のやるせない暮らしの中にも光がある。
歴史と経験に感謝と反省をもって「地」に足をつけ進んでいくこと。
それをテロワール思考は気づかせてくれる。
最後に「テロワール」を適応できる産品の条件をあげておこう。
・高付加価値な希少産品であること。
・農産物でも海産物でもありえるが、人間の加工プロセスが介在すること。
・地域の長い歴史のなかで作られてきた産品であること。
文/
京都工芸繊維大学デザイン・建築学系准教授。専門:西洋近世都市史。主な著書『近世フィレンツェの都市と祝祭』東京大学出版会、2020年

【第Ⅰ部 テロワールとは何か】 第1章 テロワール概念の成立と歴史(加藤玄)/ 第2章 近世フランスにおける「テロワール」(坂野正則)/ 第3章 近代フランスにおけるワイン法と都市ボルドー(野村啓介)/ 第4章 近世トスカナにおける原産地呼称(赤松加寿江)
【第Ⅱ部 テロワールが息づくワイン生産の現場】 第5章 サン=テミリオンとシャトーの歴史(加藤玄)/ 第6章 サン=テミリオンのワイン醸造所の敷地環境(小島見和)/ 第7章 ボルドーのワイン醸造所の建築空間(中島智章)/ 第8章 ダヴィド=ボーリュー家文書をひもとく(野村啓介)
【第Ⅲ部 テロワール概念の可能性】 第9章 シャンパーニュのテロワールと産地の形成(赤松加寿江)/ 第10章 宇治茶産地における生産と加工(上杉和央)/ 第11章 台湾茶のテロワール、その「外と内」(大田省一)/ 第12章 日本茶のテロワールと輸出(杉浦未樹)
続きを読む
スポンサーリンク
【注目の記事】
スポンサーリンク