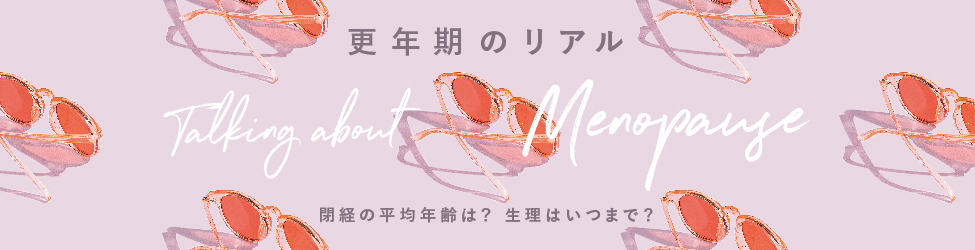源氏物語の時代から続く、日本人と香りの関係|女のギアチェンジVol.13
「いい匂い」の表現に乏しい日本人
暑い季節になるとテレビCMでもやたらと「臭い」対策を謳った商品が目立ってくる。
日本人は、嫌な臭いが嫌いである。特に自分がそんな臭いを発していると考えたら耐えられない。ただ不思議なことに「いい匂い」に関してはかなり疎い人種なのだ。
いい匂いは分かるけど、言葉にしようとすると、「さわやか」とか「芳醇」とか、わかったようなわからんような、ざっくりした形容詞で片付けることが多く、細かい表現を持ち合わせていないことに気付く。だからグルメリポートにみんな苦しむのだ。
そこへいくとフランス人は真逆だと感じる。パリの街角で適当に声をかけた人でも、ことごとく素晴らしい「食レポ」をするのである。その重要なポイントは匂いの表現で、フランス人は持てるすべての語彙を駆使して、こと細かに匂いを表し、物に例え、終いには即興でアレンジレシピまで提案してしまう。
聞いている日本人としては「ごちゃごちゃ言わんと、早よ食えや!」と関西弁で突っ込みたくなるほど、食へのこだわりは最強と言ってもいい。
そんなフランス人が、絶賛する日本食の国の住人である私達は、なぜいい匂いの表現に乏しいのだろうか。
文豪たちの食レポにも…
因みに昔の人はもう少し匂いについて多彩な表現をしていたのじゃないかと思い、食通として知られた谷崎純一郎、志賀直哉、泉鏡花の本を引っ張り出し、食べ物についての文章を漁ってみた。すると驚いた事にほぼ無いに等しかったのである。
匂いについては、「芳香尚お一層の」などとざっくり。ただし、他の描写はすさまじい。「色香ともに至純、含めば霧を桃色に披いて、月にも紅にも照添おう。さながら、食中の紅玉(ルビイ)珊瑚である」泉鏡花の随筆「真夏の梅」からの抜粋だが、梅干しも鏡花の手にかかると指輪にしてはめてみようかしらんと一瞬思ってしまう。
谷崎純一郎のかの「陰影礼賛」にも重箱の隅に穴が開くほどの細かさで、かえって理解しづらい情景描写はあるものの匂いについてはそれらと比べるとほとんどないに等しい。
これはすごい発見をした思うのだが、こんな文豪でも、パリの一般人ほどの匂いの表現も持ち合わせていなかったのだ。
香りとの付き合い方
あいかわらず、前置きが長いというか、前置きがメインになってしまった感があるが、今回のテーマはこの季節の「嫌な臭い」にどう対処するか。検証の結果?からもわかるように日本人は、いい匂いに鈍感だからこそ、嫌な臭いには敏感で手厳しい。かといって、バブルのころに流行った超濃厚な香水をつけて、職場で「香水ババア」と陰口をたたかれるのは本末転倒である。
汗をかかないことは不可能に近いとなれば、やはり何らかの「香り」に頼るしかないと私は思う。私がおススメなのは体温や汗の影響を受けにくい、髪の毛の先端あたりに柑橘系の香りを振ることだ。だから私は香りが残るタイプのシャンプーは使わないようにしている。
ここまで、汗や体臭はなるべく抑えたいよね、という前提で話を進めてきたが、最後にこぼれ話をひとつ。
源氏物語の宇治十帖に薫と匂宮という光源氏ゆかりのプリンスが登場するのだが、この薫というのは生まれつき、体から芳香が薫ったというのだが、以前、瀬戸内寂聴先生に「どういう香りだったんでしょうね」と伺ったら
「ああ、あれは私、ワキガだったと思うのよね。それがすごくセクシーな香りだったんじゃないかしら。」
とにやりと笑って仰った。
私はドン引きしつつ、確かに、当時は超濃厚なお香ももてはやされたし、今よりももっとフランス的な豊かで肉感的な香りの文化をもっていたかもしれないと思った。
それとも、恋は盲目、好きになってしまえば臭いも匂いも薫るということなのだろうか・・。
スポンサーリンク
【注目の記事】
- 「若作りが痛いオバサン顏」の原因は「黄みがかったブラウン眉」のせい?40・50代が買ってはいけないアイブロウアイテム
- 思春期ど真ん中の高2男子が変わった!ゲームと動画で夜更かし三昧→翌朝起きられない…のダラダラ生活が、スマートウオッチつけたら別人級に
- 40代以降の「肌の変化」どう向き合う? 赤のジェリーでおなじみ「アスタリフト」たった7日試しただけで「わかったこと」とは!
- 【強烈寒波の防寒はコレ!】48歳「冷えに悩む」PTA中受ママが「温活にハマった」結果、家でも外でも「つけっぱなし」!暖房代も節約できるあったかグッズとは?
- 【強烈寒波の防寒はコレ!】48歳「冷えに悩む」PTA中受ママが「温活にハマった」結果、家でも外でも「つけっぱなし」!暖房代も節約できるあったかグッズとは?
スポンサーリンク