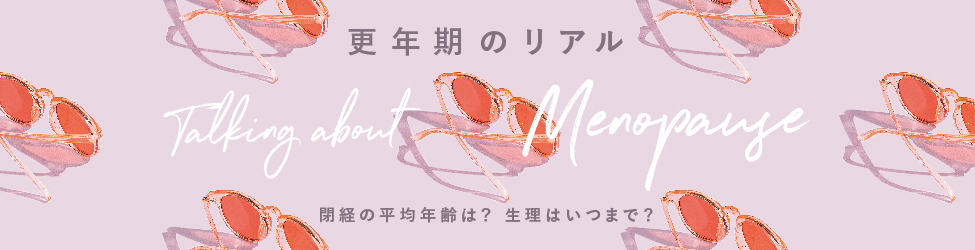「香港は死んだ」と聞いた中国人が言った。「なら、私たちはゾンビなのか?」
2020年6月30日に『香港国家安全維持法』が制定及び施行されました。
翌7月1日、産経新聞は「香港は死んだ」という一面記事を掲載します。
その後、日本のマスコミやネットの論調は、「中国=悪」という色彩で一辺倒に塗りつぶされていきました。
特定行政書士・社会学者・ベトナム国立フエ科学大学特任教授の近藤秀将です。
私は普段、アジア地域からの入管実務を手掛けています。仕事柄、香港を含めたごく普通の「生活者」としての中国人と多く接します。 中国人の視点でこの流れを見るとまた違った像が浮かび上がります。
そもそも、イギリスが中国を不当に侵略した結果、香港が生まれた
私は、「香港」に何度か行ったことがあります。その街の風景と人々の活気は、まさに「アジアを代表する都市」として相応しい存在感を持っていました。
雑多でありながも洗練された「自由市場経済の都」。
それは、一つの「奇跡」のようなもの。
そんな印象をもっていました。
ただ、同時に、私は、「香港」という存在に違和感を持っていました。そもそも、イギリスが植民地化したことから「香港」という地域が誕生したという前提があります。
アヘン戦争という、一方的にアジアを貶め、自国の利益のみを追求した「侵略」によって蹂躙されたことによって誕生したのが「香港」なのです。
イギリスが中国に麻薬を売りつけ、中国がそれを取り締まったら、イギリスが逆ギレして開戦。イギリスが香港を植民地化するという超展開でした。
本来、中国に対する植民地主義的加害者であるイギリスが、『香港国家安全維持法』の場面では、「香港の自由の守護者」みたいな立ち位置になっていることに、誰も違和感を覚えないのか。
(BBCニュースJapan『ジョンソン首相、香港の300万人にイギリス市民権への道示す』2020.7.2)
「一国二制度を守れ!」
「国際社会との約束を守れ!」
と声高に叫ぶ人々は、
イギリスが、中国を蹂躙した結果として「香港」が誕生したということを忘れていないでしょうか。
そもそも香港は「自由」だったのか?知られていない選挙制度
また、「香港」はイギリス植民地時代には、植民地官僚によって支配され、通常の「選挙」のようなものはなく、現在のような選挙制度は、中国政府によって創られたものです。
(中園和仁,1991,『Bulletin of the Sohei Nakayama IUJ AsiaDevelopment Research Programme』)
私は、加害者(イギリス)が、被害者(中国)の弁護士となっている「破綻した法廷ドラマ」を見せられているような気分で、一連の流れを見ていました。
そもそも「一国二制度」とは、香港の「憲法」ともいうべき『香港特別行政区基本法』によって規定されています。
具体的には、中国の一部である香港を「特別行政区」として、中国本土とは異なる法律等を適用する制度です。
同制度は、香港がイギリスから中国に返還された1997年から50年間維持され、2047年には、住民投票を経ることなく当然に中国本土と同じ法律等が適用されるようになります。
日本人にはわかりにくいが「一国二制度」と「香港独立」は矛盾する
この点、香港基本法第1条では「香港特別行政区は中華人民共和国の不可分の一部である」と規定されています。
したがって、「香港独立」との主張は、「一国二制度」(香港基本法)にも反するものとなります。
ですが、国安法を取り巻く一連の言説の中には、「一国二制度(香港基本法)を守れ!」「香港独立!」と相互に矛盾するようなものが入り混じっています。
また、冷静に考えれば「一国二制度(香港基本法)」は、イギリスに植民地化された「香港」を中国に名実共に取り戻すための制度です。その悲願が書き表された前文をご紹介しましょう。
【香港基本法 前文】
香港は古来中国の領土であり、1840年のアヘン戦争以降イギリスに占領された。1984年12月19日、中英両国政府は香港問題に関する共同声明に調印し、中華人民共和国政府が1997年7月1日に香港に対する主権行使を回復することを確認し、これによって、香港を取り戻したいという中国人民の長きにわたる共通の願いが実現した。
国安法が制定されたのは、返還後23年目。まさに折り返し地点といえます。
香港市民は、いずれは完全に中国本土と一体になることを理解し受け入れていたはずです。それ自体に抗うことは「一国二制度」では許されていません。
そんな当たり前のことさえ、国安法を取り巻く言説では蔑ろにされています。
「香港の中国化」は、既定路線であり、これを覆すことこそ「一国二制度(香港基本法)を守れ!」「国際社会との約束を守れ!」との主張に反します。
なんで「国安法」が必要となってしまったのか、「背景」から紐解くと
「国安法」は、香港で起きた暴動等に対応するため、第1条で規定されている通り、むしろ「一国二制度」を守るために創設されました。
国安法批判者は、この目的条項は、単なる「形式」であり、実際は、国安法は「一国二制度」の破壊者であると主張しています。
この主張は、正しいのでしょうか。
国安法批判者は、同法の犯罪類型とそれに関する手続の危険性を挙げます。国安法犯罪類型は、「国家分裂罪」「国家を転覆する行為」「テロ活動」「外国、海外勢力との結託」の四類型です。
この中で第20条「国家分裂罪」を見てみると、確かに“厳しい”という印象はあります。
ただ、国安法が規定しているのは、「国家の存立」に関する犯罪です。
であれば、“厳しい”のは当然ではないでしょうか。
あまり知られていないことですが、日本でも「国家の存立」に関する犯罪は死刑を伴う罪として規定されています。第81条(外患誘致)第82条(外患援助)第88条(外患予備・陰謀)など。
確かに「中華人民共和国」は、民主制(国民が選挙で代表者を選ぶ制度)を取っていません。
その意味では、「自由は制限されている」ことになるでしょう。
でも本当に香港市民の「怒り」は、自らの「自由を制限される」ことに核心があるのでしょうか?
香港市民の怒りの本質は「格差社会」そのものにある
私は、香港社会に広がっている貧富の格差、中間層の没落、高い実業率に対する「怒り」も大きなものとなっていると思います。
イギリス植民地時代を通じて「自由市場経済の都」として繁栄してきた香港は、実は政治的危機の前に経済的危機に直面しているのではないか。
確かに言論の自由が制限されることは、非常に重要な問題です。
ですが、それと同じぐらい、もしくは、それ以上に貧困の蔓延は問題なのです。
口は、パンのみを食べるにあらず。
口は、自由を実現するためにあるべし。
と、言ったところで、結局餓えたら終わりです。
精神的高潔性は、一部の「英雄」にこそ意味があるものでしょう。
しかし、多くの「民」にとっては、「日々の食べ物」「家族との時間」「安定」こそが必要です。
「英雄」が、自らの精神的高潔性を理由として、「民」の生活を壊してきたのは、どの国の歴史を見ても理解できるでしょう。
民主主義にしろ社会主義にしろ、それは人が豊かになり、安定するための手段です。その手段が上手くいっているうちは何であれ問題ありません。
「死んだ」という表現が15億人に対して知らずに行う侮辱
外部からはその内情がわかりにくく脅威に見える「中華人民共和国」ですが、たとえば北朝鮮のような一人の「独裁者」が長期に渡り支配する人治国家ではありません。トップの世代交代等も行われ、法律によって運営される法治国家です。
また、半世紀を越えて存在しています。約15億人の人民は、生活をしており、新しい文化も次々と生み出しています。
「香港の中国化」をもって「香港は死んだ」という表現は、中華人民共和国に住む全ての人民に対する侮辱ではないでしょうか。
中国本土出身の中国人が、私に言いました。
「なら、私たちはゾンビなのか?」と。
コロナ禍の今こそ「島国根性」を捨て、汎アジアの視点で政局を見る
かつてアジアは、イギリスやフランス等の植民地主義によって蹂躙されてきました。
イギリス等で発展してきた民主制と中華人民共和国が相反するからといって、それを一律否定することは、かつての植民地主義となんら変わりません。
我々日本人は、アジアの一員として、アジアの価値観をもって「香港」で起きていることを理解しなければならないのではないでしょうか。
最後に、アジア主義を掲げたある日本人の言葉を引用します。
引用元は、緒方竹虎先生(元副総理)が上梓された「人間中野正剛」(中公文庫,1988)です。
中野正剛(東方会総裁・ジャーナリスト・元衆議院議員)
「ここにおいてか天の使命たる汎アジア主義の大道を踏まんことを力説するなり。
しかるに世界全局に向って眼を開かざる者は、日本なる小天地に跼蹐して、シナなる対手国を狙う。
その故に齷齪たる島国根性は豆のごとき敵愾心を生み、この敵愾心を満足せしむべく、火事泥主義を鼓吹し、ただシナを圧迫し得たるを顧みて、背後に他の野心国の紅舌を吐きつつあるをしらざるなり」(129頁)
*編集部より/上記引用は原典の執筆された時代背景を鑑み、そのまま表記しています。
スポンサーリンク
【注目の記事】
- 思春期ど真ん中の高2男子が変わった!ゲームと動画で夜更かし三昧→翌朝起きられない…のダラダラ生活が、スマートウオッチつけたら別人級に
- 40代以降の「肌の変化」どう向き合う? 赤のジェリーでおなじみ「アスタリフト」たった7日試しただけで「わかったこと」とは!
- 【強烈寒波の防寒はコレ!】48歳「冷えに悩む」PTA中受ママが「温活にハマった」結果、家でも外でも「つけっぱなし」!暖房代も節約できるあったかグッズとは?
- 【強烈寒波の防寒はコレ!】48歳「冷えに悩む」PTA中受ママが「温活にハマった」結果、家でも外でも「つけっぱなし」!暖房代も節約できるあったかグッズとは?
- 脱・着太りにやっぱり頼れる【ユニクロ】。真冬の屋外イベントも怖くない、防寒と美シルエットを両立したダウンコーデ【40代の毎日コーデ】
スポンサーリンク